

NO.287
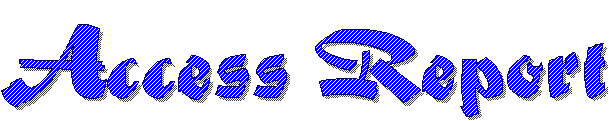
2008年10月5日
アクセス教育情報センター
目次
|
学校情報 |
公開模試情報 | 教育情報 | 教育情報 | その他 |
| 世田谷学園 | 四谷大塚9月 | 学校選択制 | 日教組と学力 | 名言・迷言・冥言 |
学校情報
世田谷学園 教育懇談会(08年9月25日)
入試広報担当 中村先生
中学生は別学の方がよい。女子の方が早熟。男子は幼い。
先日も高校2年生がカードゲームをやっていたので注意をしたら、「友だちから誘われたので、僕が悪いのではない」という言い訳をする。
1)教育理念
世田谷学園の教育理念は「THINK&SHARE」。これは天上天下唯我独尊を国際的に通用する言葉として英訳したもの。天上天下唯我独尊は自分だけ良ければよいということではない。自分が尊いのと同じくらいあなたも尊いということ。
その教育理念を実現するために、学校のモットーとして
・明日を見つめて、今をひたすらに。
明日は未来。今は自分を認識すること。
将来〜になりたい。そのために今の自分は何をなすべきなのか。
・違いを認め合って、思いやりの心を。
体の大きい子が小さな子に寄りかかれば、小さな子はそれだけでいじめられたと思うこともある。
いじめが起こるかは違いを認めあえるかどうかによる。
2)学園の様子・・映像を使いながら
・登校すると校門で一礼する。
最初は、挨拶ができない生徒がいる。おはようと言っても「うん」という返事の子も。
制服の下からパジャマが出ていたり、カバンを忘れてくる生徒も。
時間割を揃えなくていいように全てカバンに詰めてカバンがあふれている生徒も。
・入学をしたらまず友だちを作る
男の子はまず前後左右の席の子と友だちになっていく。
中1のときは女子がいないのでこの学校でよかったと言っている。それが、高校生になると女子が以内とつまらないと言い出す。幼いながら成長していく。
・1日の様子
中1の英語はクラスを分割して、チームティーチングの授業。
授業参観が5月末と11月に行われる。中1が一番参加率が高い。
昼食は弁当、食堂どちらでもよい。食堂は中1から利用できる。
中1と高3は食べる量が違う。ランチは430円。
高校生になると家で話す言葉が、メシ、フロ、ネルだけの生徒もいる。
コンピューターの授業では1人1台ずつ利用。パワーポイントを使ってプレゼンテーションが出来るようにする。
家庭科では裁縫の上手い子もいるが、ナイフの使い方を知らない子やマッチを擦った子とのない子もいる。
放課後は清掃とクラブ活動。クラブには85%〜90%の生徒が加入している。そのうち運動部が80%くらい。
・学校の1年
入学式、花まつり
オリエンテーション・・中1は4月下旬に1泊2日で。友達作りが目的。
教員はそれぞれの生徒の友達作りが上手くいっているか普段から気をつけて見ている。
男子校は自分をカッコよく見せる必要がない。
体育競技会・・5月に。クラス対抗。
世田谷学園では運動会というのはない。
サマースクール・・中1は館山に2泊3日で。
自然観察では理科の先生が説明役に。
食事前に合掌。「いただきます」は命をいただきますということを知る。
食肉市場の見学に行く。自分たちは生き物を殺して食べていることを実感し、食べ物をそまつにしないようになって欲しい。
学園祭・・10月。中1は館山での平和学習の発表やクラブ発表。
弁論大会・・中1から高3まで各クラス1人ずつの弁士が出る。
ギャラリートーク・・11月に美術館を訪問。教員が解説。
ろう八摂心・・12月に8日間の早朝座禅会。6時から。在校生の1/3にあたる450名近くが参加。自分と対峙する。
何年に1度か2度、何も考えないで座禅を組めることがある。
スキー教室・・12月20日頃から3泊4日で。中1から中3の有志で180名近くが参加。以前は教員が資格を取り指導をしていたが、今は専門のインストラクターに指導してもらう。
海外交流・・高2のカナダ英語研修(11日間)にはほぼ全員が参加。
高1では3ヶ月のカナダ姉妹校交換留学がある。
3)学習指導
基本方針は
・明日を見つめて、今をひたすらに。
・違いを認め合って、思いやりの心を。
前期・・中1、中2・・・・・自立する時期
家庭学習の定着を図る。
入学してから伸びる生徒はスケジュール管理の出来る生徒。
そのためには、夕食を一定した時間にとるようにする。
中期・・中3、高1、高2・・自律する時期
主体的な学習が出来るように。
知的好奇心を持つことが大切。
そればっかりやっているとか、この教科はいいけれどあの教科はダメねとかを言わない。
後期・・高3・・・・・・・・希望大学現役合格に向けて
現役合格に向けた得点力の養成。
4)その他
・携帯電話は学内、学外とも禁止。家庭によっていろいろな考え方があるが、学校には持たせないでくださいと言っている。
・クラス編成では中1から特進クラスを設置。特進クラス1期生が高2に。
・多彩な課外授業。
特別演習・・放課後、中2〜高2の希望者対象。
夏期講習・・中1〜高1対象。
夏期集中講座・・高2、高3対象。
受験演習・・放課後、高2、高3対象。
ステップアップ講習・・放課後、中1〜高2対象。定期試験の結果による指名制。
・学年に応じた進路指導
前期・・自己を見つめる、職業調べ。
中期・・将来設計、オープンキャンパスへの参加
高1は大学のオープンキャンパスに全員が参加。参加レポートを作成する。
高2では卒業生による講演や話を聞く。
後期・・卒業生による受験のしかたについての話を聞く。
5)進学実績 (説明会資料より)
08年大学入試結果(抜粋)
東大 東工大 一橋 北大 東北 筑波 学芸 横国 首都 国公立計
総数 3 8 2 2 2 1 1 3 5 44
現役 1 8 2 1 0 1 1 1 5 33
早大 慶大 上智 明治 青山 立教 中央 法政 理科大 ICU
総数 42 39 30 69 23 34 31 25 58 2
現役 29 30 22 46 12 24 22 10 43 0
卒業生208名に対する東大、早慶上への現役合格者数の割合(A率)は39.4%。
MARCHへの現役合格者の割合(B率)は54.8%。
国公立の現役合格者数の割合(K率)は15.9%。
5年間のA率推移は61.8%−54.5%−55.2%−39.1%−39.4%
5年間のB率推移は50.8%−42.7%−49.7%−48.7%−54.8%
5年間のK率推移は20.6%−22.7%−16.6%−11.7%−15.9%
6)09年入試要項概要 (説明会資料より)
1次 2月1日 男子 60名 4科
2次 2月2日 男子100名 4科
3次 2月4日 男子 40名 4科
入学手続きは各回とも2月6日15:00まで。
08年入試結果
1次 2次 3次
入試日 2月1日 2月2日 2月4日
募集人数 60 100 40
応募者数 242 582 494
受験者数 224 455 242
合格者数 75 331 97
合格基準点
(350点) 219 202 210
http://www.setagayagakuen.ac.jp/
町田市内三校合同 塾対象説明会(08年10月2日)
町田市内の桜美林・玉川学園・日大三の三校の塾対象合同説明会が町田文化交流センターで実施された。
1) 桜美林
高等学校教頭 藤崎先生
4月に新しいチャペルが完成した。中学は40人×4クラス・高校は40人×8クラスが定員だが、実際は中は中1は4クラス中2・3は5クラス高1は9クラス高2・3は10クラスになってしまった。
過去は女子の多い学校だったが近年は男女同数に近づいている。
クラブ活動は中学校では90%以上が参加。高1で85%高2で75%がクラブに所属している。文系クラブは中高合同で活動している。
高1は内部進学と高校受験組は別クラス。高2から合体し、文系理系クラスに分かれる。ここ5年で他大学の合格実績が飛躍的に増加し、桜美林大への進学はここ数年10%位である。(昨年は8%)今年は立教大学の合格者が増加した。
入試広報部長 平澤先生
今年の入試の一番の変更点は1日の午後入試の新設。募集定員40名で算国2科目のみの入試となる。スタート時刻は15時。
合格者は1日午前入試でたくさん出したい。昨年60名の募集定員に対して117名合格を出した。今年は午後入試新設のため午前の定員が40名になるが、合格者80名以上は出したいと考えている。
2科4科選択入試(1日午前・2日)の場合まず合格者の3分の2を受験者全体の中の算国2科目の上位から決定し、残りを4科目受験者の中(2科目で合格点に達しなかった者)から合格させる。
3日の入試は昨年同様4科目受験のみとなる。
4回の入試機会のうち3回受けた場合は一番いい得点を考慮して優遇する。(各科目の受験日ごとの最高得点を利用の意味であろう)複数回受験の場合受験料の割引あり。
通知表のコピーを提出してもらうが出席日数しか見ていない。
補欠は発表しない。その分多めに合格者を出す。追加合格を出す可能性はある(08年入試では3名出した)。
1日入試は(午前・午後とも)淵野辺駅前キャンパスで受験できるが、会場が狭いので駅前受験希望者が多数の場合は先に出願した順になる。
09年入試要項概要(説明会資料より)
09年より1日に午後入試を実施。
1回 2月1日午前 男女40名 2科4科
男女若干名 英・国
2月1日午後 男女40名 2科
2回 2月2日 男女40名 2科4科
3回 2月3日 男女40名 4科
2月1日の試験会場は本校または淵野辺駅前キャンパス(ただし英・国入試は本校のみ)。
午後入試は15:00開始。
入学手続きは各回とも2月7日15:00まで。
感想
かなり早慶・MARCHの合格実績を伸ばしている。大学進学実績の伸びを考えると昨年までの入試難度からするととても魅力的である。また、スクールバスが現在無料なので交通費の負担が少ないのもポイントになる。ただし今年は午後入試の新設によって午前入試も定員が減っているので難化は間違いないように思う。まして午後入試は合格者の出し方にもよるが、かなり厳しい入試になる可能性が高い。一方で合格者の数を読み間違えれば後半の3日入試の合格者が多いかもしれない。(報告 F.Hj)
http://www.obirin.ed.jp/hiscl/index.html
2) 玉川学園
中学部教育部長 石塚先生
玉川学園駅から校門まで3分だが、中高の校舎まで15分。恵まれた敷地の中にある。玉川学園駅から駅前の交差点の上を通り構内へ入れる直通通路を計画中。(平成23年頃?)
K−12のエリアが完成。生活エリアを小1〜4・小5〜中2・中3〜高3の4学年ずつに区切り、それぞれの校舎がある。中3は高校生と同じ場所、時間帯で過ごすことになる。
スーパーサイエンスハイスクールの指定を受け、宇宙開発機構による講演や、ソーラーカーの試作などを行なっている。
海外に16の提携校があり、年間250名近くのホームステイの受け入れも行っている。
インターナショナル・バカロレア・クラスを設置。7年生(中1)で約半数の授業を英語で行っている(英語、数学、社会、理科は英語で)。学年が上がるごとに、英語で行う科目が増える。授業は探求型の授業で、4時間の家庭学習を要求される。現在中1が15名、中2が11名。海外の大学への進学を目指す。
課外活動(クラブ活動)には7割の生徒が参加。
中1、中2では英語、数学で習熟度別授業を行う。中3から高3では英語、数学、理科で習熟度別授業を行う。
自由研究は選択制。中1から高3まで自らの計画に基づき研究を進める。
教科教室制を採用。各教室には教科担当教員が常駐し、各教科の参考書や教材が完備されている。
7時間目には全学年で特別指導を実施。一人ひとりが理解できるまで指導する。
高1、高2では土曜日を使って進学特別講座を開講。塾の講師が来て指導する。
各種検定の資格取得を奨励。玉川大学では教養課程の段階で各2級の取得が要求されている。
中学から高校へは90%が内部進学。玉川大学への進学者は50%程度。以前は80%が玉川大学に進学していたが、他大学への進学者が増えている。近隣の16大学を招いて、高2、高3対象の大学説明会も開いている。
生徒の進路希望に対応できるように選択科目も準備している。
中学の定員を減員中。1学年240名(6クラス編成に)。今年は小学校からの内部進学が120〜130名の予定で、外部募集は2月1日に80名、3日に30名の募集。
2科4科選択で、選択した教科の平均で判定。つまり、理社に穴がある場合は2科目で受験したほうがよい。平成22年度からは4科目のみの募集となる。
面接は5分程度で面接官2名。面接で落ちる子はほとんどいない。合否判定というより、預かっても責任もてないと判断した場合のみ面接で不合格になる。小学校での生活や勉強についての質問が多い。
12月13日に入試問題説明会を実施。
09年入試要項概要(説明会資料より)
1回 一般クラス 2月1日 男女70名 2科4科 面接
I・Bクラス 2月1日 男女10名 3科 面接
2回 一般クラス 2月3日 男女40名 2科4科 面接
I・Bクラス 2月3日 男女 5名 3科 面接
I・B(インターナショナル・バカロレア)クラスの3科は国、算、理社総合。
一般クラスの面接は受験生のみ。
I・Bクラスの面接は受験生と保護者。
検定料は30,000円。一般クラスの同時出願は40,000円。
複数回受験の場合、面接は1回。
補欠の発表はしない。定員割れがある場合、2月5日〜12日の間に繰り上げ合格を出すことがある。
感想
4学年毎の区分は、小学校からの内部進学者を中心に考えているように感じた。(来年は中1の半数以上が内部進学)4科目受験を選択すると4科目の平均での判定のみになるので2科4科の選択が難しい。受験者にそんなに理社が強い子は多くないと思われるが、一般的な2科目で全受験者を判定する形では無いので4科受験が不利になってしまう可能性がある。一方22年から4科目募集のみというのも受験者減少のリスクが心配である。
新しい試みのインターバカロレアクラス(国際学級)はインターナショナルスクールに近いもので、半数の授業を英語で行い、将来海外で進学したい人には興味深い。課題はかなり多く出るそうなので、入学には将来そういう道へ進むという意気込みがないと挫折してしまうかもしれない。また費用はかなりかかる。(入学金を除いて毎年160万円程度)(報告 F.Hj)
http://www.tamagawa.ed.jp/?link_id=edjp1
3) 日大三
高校校長堀内先生
来年80周年、。町田に移転して30年が経ち、地元に定着してきた。
付属であるが、今後、他大学の進学により力を入れていく。
入試広報室長本多先生
5万坪の敷地。交通の便は悪いが、環境には恵まれている。
中学では基礎力の徹底を図るとともに、多彩な行事を通じて、リーダーシップや協調性などの人間形成も図り、真っ直ぐな子を育てる。行事の度に班編制を変えている。
高校では、大学進学に向けての学力アップを図る。
授業で取り組んでいることとして、
国語・・読書マラソンでは42,195ページ読破を、漢検では中3で準2級を目標にしている。
数学・・単元ごとのチェックテストを行い、不振者はクリアできるまで追試を行う。週1時間は3人の教員によるチームティーチング。
英語・・1年生からネイティブによる授業。中3ではクラスを2分割にしての少人数制授業。
中学3年での卒業論文作成を10数年行っている。テーマは自由。原稿用紙100枚以上を手書きで(代筆やHPからの転用などを減らすため)。そのために中1、中2で新聞作りやレポート作成を行い練習させていく。
三中から三高へは、基本的に希望者全員が進学できる。年に2、3名成績不振、学習態度不良、欠席日数が多い等の理由で進学を推薦されない場合がある。成績上位の生徒で外部に出る生徒もいる。
高校は普通クラス8〜9クラス、スポーツクラス1クラス、特進クラス1クラス。
スポーツクラスは野球、アメフト、柔道の推薦で入学。
特進クラスは理数系の生徒対象。国公立、難関私大を目指すクラスで、外部の大学を一般受験する。週2回、7時間授業があり、特進クラスの生徒は部活にはほとんど入っていない。
高1では内部進学者と高校からの入学者は別クラス。
高2では文系、理系別のクラス編成。
日大進学の権利をとれる生徒は80〜90%いるが、日大進学者は40%ほどで、他大進学者が増加している。
08年3月卒業生385名
日大 160名合格
国公立 26名合格
早慶上 22名合格
MARCH 138名合格
勉強する雰囲気ができてきている。職員室の前の廊下に自習・質問用の机が並んでいる。
入試は全受験者の2科目で全体の70%を決め、残りを4科受験生から決める。難問奇問は出さない方針。
国語・・詩は出題しない。長文2題+漢字。読解の文章が長いので、長い文章に慣れておくとよい。漢字は10題。日常使う言葉を中心に練習しておくこと。記述問題では全体をふまえて答案をまとめる練習をしておくとよい。字は極力読み取る努力をする。(止めはねなどはチェックしない)
算数・・四則計算、速さ、図形、水溶液の濃度、過不足算、比例配分など。問題数が多い。基礎的な計算を速くできるように。文章題は内容を正確に把握すること。
理科・・テクニックではなく興味関心を問う問題を出題。教科書で扱われている基本事項が中心。4分野から均等に出題する。計算問題、グラフの読み取り問題、環境問題、実験に関する問題を出題する。法則や公式を意味からしっかり理解しておくこと。最近話題の環境問題に関心を持つこと。
社会・・基本的な事項を問う。地理、歴史、公民の全範囲から出題する。時事的な事柄を読んだ川柳を出題する。対策としては不得意分野を作らないようにすること。自分の周りの社会に関心をもつこと。地図や資料を読む力をつけること。
09年入試要項概要(説明会資料より)
1回 2月2日 男子110名 女子60名 2科4科
2回 2月3日 男子 30名 女子20名 2科4科
3回 2月5日 男子 10名 女子10名 2科
感想
日大の附属校であるが、学校として他大進学者の増加を目指している。今年度早慶は各9名となってきたので、今後これを2桁に乗せられるかが注目される。中高一貫生は今年度の卒業生は早稲田6・慶応7MARCH63と健闘しているが、国公立は6と日大三全体の合格数32に対して物足りない数字になっている。高校入試の難度の高い学校であるが、中学入試での人気を高めるには中高一貫6年間での成長をさらに高めていけるかにかかっていると思う。以前に比べると中学生にかなり基礎の徹底を計る宿題を多く出すなど学力向上へ向けた取り組みをしている。ただ今回の説明会でこれまでと異なる新しい取り組みなどは出てこなっかった。(報告 F.Hj)
http://www.nihon3.ed.jp/
=報告書では省略されているが高校入試の話もあり、限られた時間の中での3校の説明会はさわりだけになってしまい、もう少し突っ込んだ話が聞きたかった。高校入試の推薦合格基準や一般入試の合否の目安だけを聞きに行く人にとっては一度に3校まとめて聞けて都合がよいのかもしれないが・・・。=
公開模試情報
四谷大塚9月 合不合判定テスト(9月21日実施)
前年比0.3%(65名)の減少。男子は1.1%の増加、女子は2.0%の減少。地方の受験生が減少して、首都圏の受験生は増えているということだが。
9月の三模試は日能研模試が前年比1.2%の増加、首都圏模試が前年比3.0%の減少。
04年 05年 06年 07年 08年
男子 4科 8462 8868 10009 10388 10681
2科 430 492 487 522 352
女子 4科 6338 7082 8280 8853 8801
2科 955 693 569 475 339
合計
16185 17135 19345 20238 20173
9月三模試合計
三模試合計で前年比0.7%の減少。男子は0.3%の減少、女子は1.2%の減少。
昨年の9月は前年比1.9%の増加だった。
7月の三模試合計は前年比0.6%の増加だった。
04年 05年 06年 07年 08年
男子 4科 21737 22043 23624 24212 24431
2科 1681 2055 2050 1945 1656
女子 4科 17728 19576 22013 22994 23140
2科 4333 3559 2906 2413 1960
合計 45479 47233 50593 51564 51187
三模試志望者数抜粋 学校別 (9月度)
三模試の学校別志望者数抜粋をアクセス教育情報センターの会員のページに掲載しております。
下記をクリックしてご覧ください。
三模試志望者数抜粋 入試日別 (9月度)
三模試の日程別志望者数抜粋をアクセス教育情報センターの会員のページに掲載しております。
下記をクリックしてご覧ください。
教育情報
学校選択制 東京・江東区が見直し
(毎日新聞 9月26日)
東京都江東区は、区内全域から希望校を選択できる「学校選択制度」を一部見直し、来年度から小学校については、住所で決まる通学区域の学校への入学を原則とすることにした。選択制で地域と子供たちのかかわりが薄れてきたとの住民の指摘を受けた措置で、選択制度が全国に広がる中、議論を呼びそうだ。区教委によると、小学校は「徒歩で通える学校」を原則とする。しかし、親の希望などに配慮して選択制は残し、通学区域外への入学も認める。中学校はこれまで通り、全区域から選ぶことができる。
区教委は02年度、「学校ごとに特色を出し合い、教師の意識改革や学校の活性化につながる」などの理由で学校選択制を導入した。他区域を選ぶ割合が徐々に増え、今年度の新1年生は小学校では22%、中学校では37%が通学区域外に入学した。しかし、一方で、区民から「地元の学校に地域の子供が少なくなっている」などの意見が寄せられるようになったという。区教委は「制度を6年間やってきたが、地域と子供の関係が希薄になっている。子供たちが、地域とのかかわりを強めることを重視したい」と話している。
学校選択制廃止へ 弊害目立つ、前橋市教委
(朝日新聞 9月26日)
前橋市教育委員会は26日の臨時会で、現在計66ある市立小中学校で04年度に導入した学校選択制を、10年度を最後に廃止する方針を決めた。11年度以降、原則として市教委が指定した学区内の学校に通学するよう改める。市教委事務局は「特色ある学校づくりが進むといった利点もあるが、児童生徒数に大きな偏りが生じるなどの弊害も目立ってきた」と説明した。市教委によると、学校選択制の導入から5年目を迎えた現在、少子化などの影響もあるが、中学校では最大1学級(40人)ほど生徒が増えたり減ったりしている学校がある。減少した中学校では部活動や教科担任制に支障が生じている例もあるという。
そこで、11年度からは、小学生は自宅から1.5キロ以内、中学生は同2キロ以内にある学区内の学校に通うように改める。ただし、学区内の学校までの距離が小学生で1.5キロ超、中学生で2キロ超の場合で、かつ、学区内の学校までの直線距離の2分の1以下の近さに学区外の学校がある場合には、学区外の方に通うこともできる。あわせて、制度変更の影響が大きいとして、すでに選択制を利用して在学中の小学生を対象に11年度以降、経過措置も設ける。具体的には(1)その児童の弟や妹が希望した場合、同じ小学校に入学できる(2)その児童が希望した場合、選択制を利用して入学した小学校の学区内にある中学校に進学できる――の2点。
法科大学院縮小を 中教審、提言へ
(毎日新聞 9月27日)
法科大学院のあり方を検討している中央教育審議会の法科大学院特別委員会は、30日に公表する中間まとめで「法科大学院全体の規模を縮小すべきだ」と提言する方針を固めた。新司法試験の合格率低迷や志願者数減少が続く大学院には、自主的な定員見直しを要望。入学時の適性試験に合格最低ラインを設け、学生の質を担保することも盛り込む。国の諮問機関が法科大学院の規模縮小を提言するのは初めてで、再編統合が加速しそうだ。
法科大学院74校の入学定員は約5800人。中教審や文部科学省は、大学院の自発的な取り組みでは、教育内容や学生の質の保証が難しいと判断し、より直接的に大学院に働きかけることにした。特別委は(1)定員規模に見合う教員数を確保できない(2)入試倍率が低下し、質の高い学生が確保できない(3)修了者の多くが司法試験に合格していない状況が続く−−などの大学院は「自ら定員見直しを検討する必要がある」と提言する。教員の確保が難しい場合は、他の大学院と積極的に統合することを推奨。大学院で習得すべき最低限の内容(ミニマム・スタンダード)を設定することも求める。教員数確保のため、学部教員兼任でも大学院の専任教員扱いとすることが、13年度まで暫定的に認められているが、この措置を延長しないことも提言する。
職員会議挙手禁止通知 撤回求める
(毎日新聞 9月28日)
東京都教委が06年4月に出した「職員会議で教職員の意向を確認する挙手・採決を行わない」との通知を撤回するよう求めている都立三鷹高校(三鷹市)の土肥信雄校長(59)を支援する集会が27日、武蔵野市内で開かれ、教育評論家の尾木直樹さんらが支持を呼びかけた。集会には、市民ら約350人が出席。土肥校長が「言論の自由がなければ生徒の幸せもない」と訴えた。尾木さんは「挙手・採決を禁止するのは全国的にも『超異常』だ」と話した。
日教組と学力 中山説、調べてみれば相関なし
(朝日新聞 9月27日)
「日教組(日本教職員組合)の強いところは学力が低いんじゃないか」――文部科学相時代に全国学力調査を提案した中山国土交通相が、テストで何を調べたかったかについて、こんな「本音」を明かした。「現にそうだよ。調べてごらん」。しかし、データをたどってみると、成績トップの秋田の日教組の小中学校組織率が5割超で全国平均(34.1%)を大きく超えるなど、全体的な相関関係はうかがえない。現場の先生も「短絡的」とあきれ顔だ。
「日教組の子どもなんて成績が悪くても先生になるのですよ。だから大分県の学力は低いんだよ」
教員採用不正事件を引き合いに出しながら中山氏がやり玉にあげた大分は、小中学校の日教組の組織率が6割を超える。今年の全国学力調査では、小6、中3の全科目で、平均正答率が全国平均を下回った。この点だけをみれば発言は「当たっている」ようにもみえるが、科目によって結果はばらつく。小6国語Aでは全国平均と2.9ポイントの差が付いたが、小6算数A、中3国語Aでは、わずか0.2ポイント差だ。では、調査の成績が良かったところはどうか。中山氏の出身地で選挙区でもある宮崎は、小6の2科目と中3の全科目が全国平均を上回るまずまずの成績で、組織率は1割未満。ところが、小6の全科目でトップ、中3もすべて上位3位に入った秋田の組織率は5割以上。組織率が9割近くと全国トップを誇る福井は、中3の3科目で1位だった。
「中山説」では、成績の低いところは日教組が強いはずだが、小6、中3の全科目で最下位だった沖縄の組織率は4割弱にとどまる。中3の全科目でワースト2位だった高知に至っては1割に満たず、何ともバラバラだ。
東京都内の中学校長は大臣発言に対し「短絡的だしピンぼけだ。だいいち日教組にそんな力はないのではないか」。ある自治体の教育長も「日教組にどんな恨みがあるか知らないが、個人的な思いを国政に反映させるのはとんでもない」。
中山氏はインタビューで、自説が確認できたとして「学力テストを実施する役目は終わった」とも話した。新潟県の小学校教諭は、調査に疑問を感じながらも、学力向上に生かそうと励んだ。「地域で成績の差は確かにあるけど、それを改善するのが調査の目的だったはずだ。頑張ってきたのに、あの一言はないだろう」と憤る。
沖縄県の小学校教諭は、調査の前、放課後の補習に追われた。テストのための勉強で、とても児童の学力がついているとは思えなかった。「やると言い出した本人がもう必要ないと気づくくらい無駄なテストなのだから、早くやめた方がいい」
◇
対象学年の全員を対象とする全国学力調査のそもそもの発端は04年11月。当時文科相だった中山氏自身が改革私案「甦(よみがえ)れ、日本!」で導入を表明したことだった。当時は目的について「競い合う心や切磋琢磨(せっさたくま)する精神が必要」と説いていた。
その直後、国際学力調査で日本の順位が落ちたことなどもあり「学力低下問題」への対応策として急浮上。05年6月には、小泉内閣の「骨太の方針2005」に盛り込まれた。同年10月の中央教育審議会の答申は「子どもたちの学習の到達度・理解度を把握し検証する」と明記。国策として統一的に学力の様子を調べる必要性が強調され、毎年60億円かかるテストの実施へと進んでいった。
今回の発言について、文科省には「あれは前からの持論だから」と冷めた受け止め方をする向きが多い。「別の役所の大臣だから」「『信念』をどこまでも語っちゃう人」「免疫できてます」。担当者の一人は「組合がどうのという目的はないし、役目が終わったということもありません」と話した。
=「政治家の子供は学力が低くても政治家になれる」「総理大臣の子供は学力が低くても総理大臣になれる」という疑問を解消するために、世襲政治家の学力調査をやってもらいたいもの。=
神奈川県立山北高 退部生徒に保証書
(毎日新聞 9月27日)
県立山北高校(山北町)の井上孝一校長が、部活顧問の男性教諭(48)に半ば強制的に退部させられた女子バレーボール部の2年生6人に「3年間、バレー部で活動した」という内容の“保証書”を発行していたことが分かった。保護者は「虚偽内容の文書をもらっても経歴詐称になる」と困惑。相談を受けた県教育委員会は公文書偽造の疑いがあるとして近く事実関係の調査に乗り出す。
同高や保護者らの説明によると、同部ではレギュラーを巡って1、2年生の間で感情のもつれが生じ、顧問は11人いる2年生の練習をあまり指導しなくなった。6月初旬の高校総体県大会で試合に負けた後、顧問は「2年生全員をクビにする」と話し、同16日のミーティングで「部活解散」を宣告した。翌17日の朝練習に参加した2年生7人は、顧問から「おまえらは練習をやるな。体育館から出ろ。練習をやめろ」と強い口調で言われた。放課後には3年生から「ボールを使うな。部の備品に触れるな」と言われ、やむなく退部に追い込まれたという。
2年生6人の保護者が8月17日、学校を訪れ、井上校長に退部理由の説明や「強制的に退部させられた形では子供たちが困る」と部活への復帰を求めた。井上校長は「こうすりゃ、いいんでしょ」と言い、保証書を用意。学年とクラス、氏名の記入欄があり「上記の生徒が3年間にわたり本校女子バレー部において活動し進路等の資料に明記し保証するものとする」と記されていた。保護者たちは今月18日、県教委を訪れて、応対した職員3人に保証書を見せ、「虚偽内容の文書が通用しますか」とただした。職員は「ありえないことだ」と校長の不適切な対応を認めた。
井上校長は毎日新聞の取材に保証書について「私の勇み足」と非を認めたうえで「『うちの娘をどうしてくれる』と迫られた。退部した生徒がボール拾いなど何らかの形で部活に携わったことにして、進路保証をしてやらなければいけないと配慮した。『生徒は頑張りました』という形で保証書を出した」と釈明。「保証書には学校印を押していないし、近く保証書の撤回を求める」と話している。また、顧問教諭は「強制的に排除はしていない」と弁明している。これに対して保護者たちは、「2年生部員は部活を続けたいと希望したのに、顧問から無理やりやめさせられた。いいかげんな保証書を出して子供も保護者も黙らせようという、やり方は許せない」と学校側の対応を批判している。
県内の高校約180校に女子バレーボール部があり、山北高は県大会で8強入りするなど県西地域の有力校として知られている。
関連記事
県立山北高女子バレー部問題 不適切、厳正に対処(毎日新聞 10月5日)
◇保護者会で校長謝罪
神奈川県立山北高校(山北町向原、井上孝一校長)の女子バレーボール部を巡る問題で4日、保護者説明会が同高で開かれた。県教育委員会の担当課長は「不適切な行為だった」と認めたうえで「厳正に対処したい」と話した。
保護者会では、まず井上校長が「ご心配と迷惑をかけた。不適切な行動、判断で混乱を招いたことについておわびしたい。県教委の力を借りながら、よりよい学校運営に全力を挙げたい」と謝罪。学校側から問題の経緯や新聞報道の内容について報告した後、県教委の考え方などが説明された。
◇保証書問題
井上校長が退部した部員に3年間活動したとの保証書を発行した問題について、県教委の薄井英男・行政課長は「内容ばかりでなく、保護者に期待を持たせたことと併せ、不適切であると考えている」とし、「保証することができない内容で、校長は履行する義務のないもの。保証書を撤回するよう指示した」と説明した。保証書が公文書偽造に当たるのではとの指摘について「顧問弁護士とも相談した結果、公文書偽造や虚偽公文書作成には当たらず、刑事上の問題にはならないとの見解をもらった」とも述べた。
薄井課長は「さらに事実関係の調査を進め、厳正に対処したい」と話した。県教委は、信頼回復と学校運営立て直しのため、校内運営全般に幅広い知識を持つ元校長を「教育指導専門員」として9月30日から同高に配置、井上校長らに適切なアドバイスをしていると説明した。
◇部費会計問題
女子バレーボール部の部活顧問を務める男性教諭(48)が保護者から多額の部費を集めながら、出納簿を作成していなかった問題では、薄井課長が「使途不明金は認められなかったが、会計処理で適切さを欠いていた」との見方を示した。薄井課長によると、保管されている領収書について、発行元に照会したり関係者から聞き取りしたりして、部活動で支出した額を積み上げた結果、部費として徴収した額を上回っていることが確認された。このため「着服など犯罪性はないと考えている」と説明した。さらに「私費会計基準に沿った手続きを取るよう指導したが今後、厳正に対処したい」と話した。さらに小泉いづみ・保健体育課長は「処分になるかは不明だが、措置が決まるまで9月29日から当面の間、顧問に自粛するよう申し渡した」と述べた。顧問教諭は9月1日、井上校長から「一定期間」の部活動指導停止を命じられた。さらに自粛としたことについて小泉課長は「事態の収拾と沈静化を図るためだ」と話した。
その他
名言・迷言・冥言
(落語 堪忍袋より)
堪忍のなる堪忍は誰もする
ならぬ堪忍するが堪忍。堪忍の袋を常に胸にかけ
破れたら縫え破れたら縫え。
学校体育のあり方
(毎日新聞 9月27日)
学校体育の現場に長年いた先生が嘆く。「昔は『体育(運動)をすると脳みそまで筋肉になる』なんて言われた」。よく聞かされた「遊んでいないで勉強しなさい」も同様の発想に基づいている。米イリノイ大学の研究グループによると、小学校3年生と5年生を対象に調べたところ、運動が得意な子どもほど勉強の成績もいい、という統計学的傾向があるそうだ。
今月上旬の日本体育学会で、「エビデンス」という言葉を耳にした。科学的知見とでも訳せばいいだろうか。大学での学問研究の成果と、学校現場での実践が乖離(かいり)しているのではないか、との問題提起がなされていた。
体育とは何を教え、習得させる教科なのか? 30年以上前の自分自身の学校時代を振り返ってみれば、息抜きとして、何となく体を動かしていたという記憶しかない。「オフサイドはなぜ反則か」などの著作がある中村敏雄氏(元広島大学教授)が自身の経験を踏まえて書いている。「教えるべき内容がなく体系化もされていなければ教師はスポーツのコーチャーになるしかなく」「『レベルの低い部活指導』のような活動を体育というべきではなく」。高校の学習テーマとして中村氏は、バレーのサーブが落ちる理由やアマチュアリズムの歴史などを挙げている。体育の理科であり、社会科だ。学校体育への誤解は根強い。政治家との会合に出席したある研究者が漏らした。「筋肉マンを養成すればいい、とでも考えている政治家がいる」。自民党スポーツ立国調査会の会長でもある麻生太郎首相は、違いますよね?
=最近、公立中高では体育科出身の校長が増えているとのこと。教育委員会の指示をよく聞くのが重宝されているらしい。=
政治家の世襲 「甘え」と「甘やかし」の連鎖−−神田紫さん(講談師)
(毎日新聞 10月6日)
講談や落語など芸の世界では、親がやっているからというだけの理由で、その地位を引き継ぐことはできません。お金を積んでも実力はつかないし、芸が身に着かなければ後援会だって作ってもらえない。師匠の門をたたいたら、時間をかけてコツコツと修業し、実力を伸ばすしかありません。落語家の林家木久扇師匠・木久蔵さん親子のように、実の子が親の名前を受け継ぐこともまれにありますが、それも実力があっての話。むしろ、親に人気があると、かえって風当たりが強くなることもあります。だから、政治家の世襲を見ていると、いいかげんおやめになったら、と言いたくなります。本来、何もないところからスタートすべきなのに、世襲ならばもれなく「地盤」「看板」「カバン」がついてくる。講談に例えるならば、いきなり真打ちから始めるようなもの。そこまでの道のりが大変だからこそ、この先のつらいことも我慢できるし、どこに出ても恥ずかしくないだけの自信や誇り、根性を培っていくのに。
安倍(晋三)さん、福田(康夫)さんが2代続けて首相の座を放り出すのも無理はありませんよ。一国のあるじとしての精神力や忍耐力を身に着ける過程を省いたんですから。彼らが辞任した時、私は思いましたよ。「やっぱり、お坊ちゃんはダメよね。甘ったれ、根性がない」って。だから、申し訳ないけども、麻生(太郎首相)さんも期待できません。まあ、民主党の小沢(一郎代表)さんも世襲なのですけれども。だいたい、彼らは小さなころから、私たちよりもよほどいい暮らしをしているんでしょう? 食料品やガソリンなど、1円単位の値段の移り変わりに泣き笑いする生活なんて、きっと想像もつかないはず。そんな人たちだらけの国会や内閣が、果たして本当に庶民の生活をよくしてくれるのでしょうか。
世襲とは、要するに甘え、甘やかしの連鎖だと思います。親も後援会も子供を甘やかし、子供はどっぷりと周囲に甘える。それが何代も先まで続いていく。おいしいとこ取りで、自力ではい上がろうとする人たちをあざ笑うかのようで、何だか天下りにも似ています。小泉(純一郎元首相)さんにもがっかりしました。次男に地盤を継がせるなんて、「自民党をぶっ壊す」と言った人のすることでしょうか。獅子は我が子を千尋の谷に突き落とすといいます。小泉さんにはぜひとも、息子に「お前はゼロからやれよ」と突き放してほしかった。でも、ライオンヘアの小泉さんといえども、息子にはライオンになり切れなかったんですね。もしもですよ、何十年か先、この次男が首相になったら、また政権を投げ出すのでしょうか。選挙で世襲の政治家を吟味する時は、最低限、先代、先々代のイメージとは切り離し、その人の実績や経歴に注目しましょう。親の七光りは、親と同等、またはそれ以上に活躍する根拠ではないのですから。