

NO.228
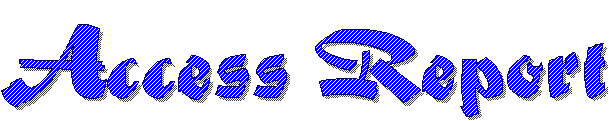
2007年 1月 5日
アクセス教育情報センター
目次
|
学校情報 |
公開模試情報 | 入試情報 | 教育情報 | その他 |
|
聖光学院
|
三模試学校別志望者占有率 | 応募状況1 | 東京大学 | 名言・迷言・冥言 |
学校情報
聖光学院 教育懇談会(06年12月19日)
校長 工藤先生
1)概要
自分は5代目の校長。聖光学院の卒業生。それまでは外人の校長が続いた。
最近の読売ウィクリーに聖光学院の授業が取り上げられる。その中で、オフコースを生んだ芸術講座と紹介されているが、彼らが在学していたときには芸術講座はなかった。彼らは3期生。ヤマハミュージックコンテストで2位になって世間に認められる。当時、学内でフォークソングの演奏を受け入れる下地があった。文化祭で彼らが演奏するのを見て、最終日に、ある先生(後の4代目校長)がアンコール演奏をみんなの前でやらせたこともあった。
創立当初は初代校長のリーダーシップが強く、管理的な時期が20年~30年続く。
聖光学院が創立される10年前に栄光学園がスタートしており、当初は栄光学園と同じ点が多かった。
教科書も英語、倫理は栄光学園と同じものを使用。中間体操もやっていた。
一体となった机と椅子(授業中、机や椅子を動かす音がしないように)、クラブ活動も週2回(現在は自由)、生徒会もなし(現在はあり)なども栄光学園と同じだった。その頃は、栄光-聖光と言われ、東大合格者数でも大きく離れていた。
その後、小さな事にこだわらず、聖光学院は聖光学院らしくという方針になり独自色を出すようにする。
2)特色ある講座
公立校は先生がある期間で変わってしまうので、時代の流れとともに学校が変わっていってしまう。昔は公立でも同じ学校に長くいる先生がいたし、卒業生が教員として戻ってくるということがあったが。
私学は良くも悪くも先生が長くいるので、卒業生が学校にきたときに自分を知っている先生がいる。現に、聖光学院には自分が在学中のときの先生がまだ10名近くいる。
私学はその地域で文化を発信する責務があると思っている。
聖光学院としての文化を発信するために選択芸術講座や聖光塾を始める。5年目に。
選択芸術講座
中2対象。土曜日の3、4時限目を使って。
バイオリン、ギター、フルート、絵画、書道、陶芸、演劇など12講座を設置。講師は一流の先生にお願いしている。
1講座20名弱。毎年、学園祭の時と2月に発表会を行う。
芸術を通して自分をどう表現するかという中で生徒の性格が出てくる。
聖光学院の中に文化を作る手段として芸術選択講座を導入したが、その後、文化祭で生徒発表が増えている。
聖光塾
教科や学年の枠を越えて、生徒の知的好奇心を刺激するものを取り上げる。
遺伝子の組み換えや裁判の傍聴など授業の中でできないことをやる。
里山の自然や海辺の生物の観察など中1、中2向けの講座もある。
天体観測講座は八ヶ岳で行う。
関心のある生徒はもとより、友達に誘われて受講した生徒も刺激を受けている。
選択芸術講座や聖光塾を通して生徒の底辺を広げたい。英語、数学を詰め込んでもその生徒の底辺は広がらない。
聖光学院も創立50年を迎えるにあたり、その方面に手を広げられるようになった。
聖光学院は東大合格に特化することはないし、大学合格者だけの人数を競う必要はないと思っている。
学校としては生徒を人間として成長させたい。
3)塾いらず
横浜には昔、塾・予備校がなかった。塾・予備校に行かなくても済むようにするために、学校が面倒を見るしかなかった。
それが、聖光学院に行けば塾・予備校に行かなくてもよいというふうになった。
中学生は最低6時間は寝る必要がある。
23:00~24:00の間には寝るところから逆算して、家で2時間は勉強して欲しい、通学に1時間から1時間半を見込む、そうすると18:00には学校から帰らせたい。クラブのない場合は16:00か17:00には帰る。
しかし、塾・予備校に通うとそうした生活のリズムが崩れる。そこで、塾・予備校に通わなくても大丈夫にする。それが定着して、聖光学院の伝統になっている。家庭学習の課題を2時間分は与える。
ただし、生徒に塾・予備校に行くなとは言わない。鎖国主義は取らない。
4)生活指導
聖光学院は生活指導が厳しい、真面目という印象を持たれている。
カトリックのミッションスクールとしてある程度の生活指導は行う。社会生活にある程度の規制は必要。
携帯電話は校則では禁止になっているが大半の生徒が持っている。携帯電話を持たせるかどうかは家庭の判断。
保護者と子供との距離感による。
高校になって子供のカバンの中を見る親や、見られて平気な子供では困るし、学校としても生徒のカバンの中を見ることはしない。生徒も建前と本音の違いがわかっており、そこに生徒と学校との適度な距離感がある。
学校のそうした対応を保護者としてどう思うか。それも学校を選ぶ材料の一つになる。
そう言う意味では、生活指導を行うが思われているより穏やか。カバンも自由。学校指定のカバンはない。帰りの立ち寄りも構わない。ただし山手駅(最寄り駅)の周りのコンビニには寄るなと言っている。
1学年200名強の人数なので、保護者、生徒と話し合える。
大学進学に耐えうる学力をつけるのは学校の基本的な立場だが、Be Gentlemanとしての生活指導は行う。
生徒のズボンの折り目で母親の対応がわかる。欠席届を出す場合も、万年筆できちっと書いて封筒に入れて出す人もいれば、ボールペンで記入しただけの人もいる。
当初は中学入試で両親面接を行っていた。本音としては今でもやりたい。面接があるから受験しないという層もあるわけで、学校に共鳴してもらえるかどうかは重要なこと。試験も2日間行っていた。
「万葉の湯」事件
学園祭の時、学校に泊まれるようにして欲しいという要望があったが、認めなかった。学園祭の打ち上げの時も23:00以降に街をうろつくことのないようにと注意する。ところが、学園祭の時に何人かの生徒が健康ランド「万葉の湯」に泊まる。早出の先生が朝早く公園でたむろしている生徒を見つけて発覚。
それに対する家庭の対応がさまざまだった。生徒に宿泊代を渡していた家庭、友達の家に泊まるからと言われて許可した家庭、今日は遅くなったから帰れないと言われ泊まりを認めた家庭。
教員の価値観も違う。親が認めているのだからよいではないかという意見もあった。しかし、外泊を認めると泊まるだけでは済まなくなる。結局、23:00以降、生徒が外を出歩くのは認められないということで、生徒説諭と保護者との話し合いをして終わる。
5)国語教育
国語教育に力を入れている。
中1、中2で10年前以上から群読に取り組んでいる。黙読による読解中心の受験国語からの脱却をはかり、じっくりと言葉と向き合う機会を作る。群読を通じて、読む・書く・話す・聞くのバランスの取れた、総合的な国土力の口上がはかれる。
中2で週1時間文章表現の時間がある。感想文や作文ではなく論理的文章の作り方を学ぶ。その時間に書いたものを教員が添削。広い視野に立ったうえでの分析力や判断力を育成する。
6)海外研修、海外交流
ホームステイは18年前から実施。中3の夏休みと春休みを利用し、希望者対象だが100名近くが参加している。
夏休みはカナダ3カ所、イギリス1カ所。春休みはニュージーランドに。
ホームステイをしたから英語ができるようにはならないが、文化の違いに気がつく。
国際交流として、今年はドイツに1名、エクアドルに1名行っている。外部の国際交流制度を使って1年間。戻ってきたら同級生と同じ学年に戻すので、1年下がらなくてよい。
私学の男子校というのはある意味では人脈作りの部分もある。学校での縦(先輩、後輩)、横(同級生)のつながりが、社会に出て40代、50代になったときに生きてくる。その意味では、学業的にきつくとも、留学して戻ってきたときに同級生のいる学年に戻れることは大きい。国内の転勤の場合も同じ。1年で戻ってくれば同じ学年に戻す。子供のために夫婦が離ればなれになるのは日本くらいではないか。
こうした校長の裁量を生かした対応は私学だからできる。
入学後に下宿生活になってもかまわない。ただし、仲間の溜まり場にするなと言っている。
よく言えば寛容、ある意味ではいい加減な学校。
他に、横浜ロータリークラブの企画で台湾の研修旅行に3名を派遣したり、水源林の伐採や、横浜港のドラゴンレース、横浜マラソンのボランティアなど若い人の力を必要とするところで協力している。
外国からの訪問客の受け入れも積極的に行い、交流会では徴兵制について意見交換をしこともある。
校長としてそうした形で学校と社会との接点とつくる仕事をしている。進学指導などは担当の先生に任せている。
7)クラブ活動
男子が1学年200名以上いるので、中学は強い。
バスケットは3年前には県の中学生大会で優勝。
軟式野球は高校も何年かに1度は県で優勝。(硬式野球部はない)
サッカーは神奈川私立中大会で優勝を目指している。
ソフトテニスやバレーボールは人数が少ないからすぐレギュラーになれる。人数の多いクラブで我慢して続けるか、レギュラーになりやすいクラブに変わるかは本人次第。
囲碁・将棋部は中学生は神奈川で優勝。見ていると囲碁の力と学力は相関関係がある。
全国高校クイズ選手権に出場しろと勧めていたら06年に達成。そのグループには校長賞(3千円の図書券)を出す。
クラブの指導も専門家に任せる。教員には放課後の仕事(クラブ顧問、補習、担任業務、校務分担など)もあるので仕事に優劣をつけてあげる必要がある。教員には授業と担任としての仕事を重視してもらいたい。クラブの指導は外からコーチを呼ぶ。教員の顧問は専門外の場合が多く、ついつい精神論になってしまい、指導者としてふさわしいのか問題。専門家をコーチとして呼んで専門家による指導を受けるようになったら、生徒はクラブを辞めなくなった。
8)単位履修不足問題
神奈川の私学では当初5校、その後7校が新聞に取り上げられる。
聖光学院もその中の1校。家庭科の履修時間が足らないと言われる。
高3は3月12日から5日間集中授業を行うことに。最終日にバーベキューをやるので、それが大学入試の祝勝会になるようにしなさいと言っている。
来年以降のカリキュラム編成にあたって、私学としてのスタンスをどう出すかが課題。
文部科学省の認める中等教育学校か併設型の中高一貫校になれば、正式に先取りができる。(高校内容を中学でやっても履修したことになる)・・併設型の届け出をする。
全必修科目を入れるために、大学入試科目の時間数を削るか、7時間目を作るかになる。聖光学院としては7時間目は作らない。クラブ活動に影響するから。定期試験の後に集中合宿を3泊4日で行う。その分費用がかかるが。
多くの学校で、家庭科、情報、世界史、理科総合が履修単位の関係でひっかかってくる。家庭科は男女平等で男子も必修になったが、女子も選択でよいのではないか。理科総合はそもそも理科ができない生徒用の科目。
私学を選ぶと言うことは公立にない部分を求めて来られるわけで、その期待にどう答えるのか(カリキュラムをどう編成するのか)これからも考えていかなくてはいけない。そこに私学の独自性があると思う。
9)保護者を見ていて
親が子供に対して、こうしたらこうなると先ばかりを見すぎているように思う。
そのため、子供にいろいろと言い過ぎている。
子供の命は神から与えられている。こどもは与えられた命を日々積み重ねて行くことが大事。
親が、自分のできなかった夢を子供にもとめるのは、子供を押しつぶしてしまうことになりかねない。
明日どうなっているかはわからない。すべて科学的に分析できたり、こうしたらこうなるということはありえない。
今日一日生きられたことに満足すればよい。朝、目覚めることの奇跡に感謝する。
いい大学に行ったからいい人生を送っているとは限らない。
愛とか神様といった目に見えないものが大切。それを大切にする姿勢を子供達に伝えていくのがミッションスクールの使命。
目に見えないものの大切さに気づいたときに子供は立ち上がる。
目に見える物質で動機付けするからおかしくなる。
10)入試に関して
06年入試結果
1回 2回 帰国
募集人数 175 50 若干
応募者数 785 1098 129
受験者数 703 673 125
合格者数 251 126 30
中学入試の日程が2月2日、4日。早稲田、慶応の附属は厳しいから聖光学院にという層が多い。
多摩川沿いの人は聖光学院に目が向いているが、都内ではまだまだ知られていない。
時事問題を出すかどうかはいつも学内で議論がある。
2回受けたら繰り上げを出す場合に有利。
1回目からの繰り上げを出す場合も、2回目の出願がしてあれば考慮する。2回受けさせるのはかわいそう。
150字の記述は50字以上ないと採点しない。
受験番号は合否に関係ない。
2回目からの繰り上げは少ない。ここ数年10名~15名。
1回目の方が合格しやすい。
帰国生入試の出願が149名に。これまでで最も多い。
願書は有料。無料だと大切に扱われない。同じものがいくつもたまってしまう。
願書も在校生の授業料の中で作成している。その授業料をお母さんがパートで働いて払ってくれている家庭もある。それを無駄に使いたくない。
11)その他
自学自習用の施設を作る。高3生に放課後21:00まで解放。毎日、20名~30名が残って勉強している。軽い食事を作る設備もある。
校舎が建設されて50年に。創立55周年くらいを目処に全面建て替えを予定している。
仮校舎を使わなくても建て替えは可能なのでご心配なく。
学内に食堂があるので、母親は自分の体調が悪いときに助かる。これは女性の先生から是非強調して来てくださいと言われた。
私学は隠れた専門店でよい。中学入試は大衆に認知されればされるほどダメになっていく。
聖光学院みたいな学校があってもよいと思っている。
(当日の話を項目毎に分けて再構成してあります・・・報告者)
http://www.seiko.ac.jp/
公開模試情報
三模試学校別志望者占有率(神奈川地区)
三模試の総志望者数の中で各模試の志望者の割合がどう変遷しているかを01年11月と06年11月で比較。
志望者成績分布抜粋
11月の首都圏模試と四谷大塚模試のデーターによる志望者の成績分布。
入試情報
応募状況1
寮のある学校の東京入試 (各校とも東京会場1回目入試の応募者数)
07年 06年 05年 04年 03年 02年
函館ラ・サール 752 660 565 568 544 424
那須海城 1292 1204 1032 1029 724 406
土佐塾中 2987 2138 2119 2225 2399 2282
西大和 520 448 379 223 105 --
佐久長聖 1054 1263 867 651 430 173
長崎日大 1130 395 -- -- -- --
=那須海城は1月6日現在。各校の入試日程が重なったにもかかわらず、佐久長聖を除き応募者数を増やす。07年の首都圏中学入試は厳しくなると言われているので、事前に入試を体験しておこうという層が増えたものと思われる。=
受験直前の心のケア 親子で上手に乗り切る方法
(朝日新聞 12月8日)
年が明けると、いよいよ受験シーズンを迎える。特に、中学受験の小学生には荷が重いことだろう。親としてもついつい、肩に力が入りすぎるのでは?それが子供に伝染して悪影響のないように。
「2学期のちょうど今頃からが、いちばん苦しかったですね」と振り返るのは、2人の娘の中学受験を体験した神奈川県の中曽根陽子さん。自らの体験から情報交換の場の必要性を痛感し、中学受験生の母親を対象にしたホームページ「ワイワイネット」を主宰している。今年2月には、ホームページに集う母親の声を中心に、いまどきの受験事情をまとめた『後悔しない中学受験』(晶文社出版)を出版した。「特に大変だったのが、長女の受験の時です。親自身、何もかも初めて。その不安を子供に気取られないように、勉強の進捗状況を見守ったり、健康管理に気を配ったりしなければなりません。しかも今頃からは学校説明会や願書の購入など、親の用事も増えてきます。心身ともに追い詰められ、本当に憂鬱でした」
子供たちも正念場であることは重々承知。ストレスから言葉づかいや態度が乱暴になったり、兄弟をいじめたり、親に反抗的になる子も珍しくない。
●否定的な言葉で悪循環
中曽根さんも毎日のように、長女とのバトルがあった。「中学受験期は、思春期のさしかかり。女の子は男の子に比べ、大人になるのが早いですし、今から思えば、甘えたいのに甘えられない苛立ちがあったんですね」
一方で、ワイワイネットを訪れる男の子の親からは「子供に受験生という自覚が薄く、やきもきする」という声も聞こえてくる。
親子ともども泣き笑いの日が続く受験レースの最終コーナーだが、暗い話ばかりではない。
小学校教諭を経て、親子や教師にコーチング指導をしている大石良子さんも、「この時期まで頑張った子は、プレッシャーにつぶされることはない。目標をしっかり立てて、着実に日々の勉強を集中してこなせば、実りある結果が得られます」
と、太鼓判を押す。「さすがにこれからは、できる子でも落ちる不安が高まる。でも、それは子供にとって、いい経験。勉強ができない子の気持ちが分かったり、自分の弱さを見つめたりする心のトレーニングになる」
と話すのは、精神科医で中学受験に関する著書も多い和田秀樹さんだ。
それなのに理想通りにいかないのは、子供に迷いや不安があるから。そして、子供を惑わせる原因は、なんといっても、親の態度と精神状態にある。
11月中旬から12月にかけて、塾の最終個人面談が始まる頃には、多くの子供が第1志望を固め、憧れの学校に受かりたいという強い意志を持っている。この目標がぶれない子は、納得して勉強に集中するので、受験体験を人生の糧にできる。ところが、親が心配のあまり第1志望を無理に変えさせたり、勉強にうるさく口出ししたり、能力以上の課題を与えたりすると、子供は萎縮し、やる気を失う。
「よくも悪くも家族でもっとも影響力が強いのがお母様。本心ではどのお母様もうちの子はすばらしいと思っている。でも、心配や不安から、子供にはつい否定的な言葉をかけてしまう。そうなると、子供は親の真意を察してはいるものの、素直になれなくて、態度が硬化する。悪循環にはまるパターンです」
●一歩引いて行動観察
特に口にしてはいけないのが、右下の表のようなNG言葉だ。母親も限界まで踏ん張っているため、感情にまかせて心にもないことを言いがちだが、親子関係に一生消えない溝をつくりかねない。それよりも、頑張りを認めて成長を喜ぶ言葉をかけるほうが、よほど子供の力になる。
大石さんは、自分を見失いがちな親子のために、ストレスサインのチェックを提案する。行動を具体的に観察すると、改善策が見つかりやすいからだ。
「このチェックは子供だけでなく、自分の行動や夫婦関係を見直す時にも役立ちます。一歩引いた立場から行動を観察することが、心の余裕を生むコツです」(大石さん)
また、模試の結果にも一喜一憂しないことだ。模試は標準の実力を測るテスト。実際の試験問題には学校それぞれの傾向がある。模試が悪くても、志望校の試験の傾向と子供の得意分野が一致していれば受かる確率は高くなる。
四谷大塚入試情報センター所長の和田吉弘さんは、「模試のおかげで本番前に自分の弱点が分かってよかったね、と慰めるくらいの余裕が欲しい」
と話す。高得点でなくても合格すればいい、と発想を切り替える。厳しく叱ると、一つも間違えられないというプレッシャーから、子供はかえって本番に弱くなる。
そして、これからの時期、今まで以上に問われるのが、父親の存在感だ。最近は受験に積極的に関わる父親も増えてきたが、まだ少数派。妻に任せきりだったり、夫婦の考えが食い違っていたりすると、母親は孤独感と不安感から子供に必要以上に厳しく当たるようになる。そうなると、子供は安心して勉強に集中できない。
冒頭の中曽根さんも、心の支えになったのは夫のサポートだった。算数の成績が思うように上がらないため、夫に勉強を見てほしいと頼んだところ、家庭の中が落ち着いてきたという。「仕事が忙しいので朝に1問だけ一緒に解く『家庭教師』でしたが、夫も次第にのめりこみ、通勤の合間に一生懸命、勉強していたようです」(中曽根さん)
●相手の言葉を繰り返す
単身赴任中でも可能な限り週末は自宅に帰り、子供と一緒に食事をとる。父親が願書を取りに行き、ついでに学校を見学してくる。子供が煮詰まっている時には散歩に誘ったり、時間を決めて一緒にゲームを楽しむ。短時間でも父親がサポートできることは多い。夫婦の間でも、夫に愚痴を聞いてもらうだけで、妻はずいぶん肩の荷が下りる。
ただし、話の聞き方にはコツがある。受験に距離をおいている夫は俯瞰的に現状を把握できるだけに、今後の作戦を端的にアドバイスしがちだ。しかし、これが夫婦ゲンカの火種になる。毎日必死で子供と一緒に戦っている妻からすれば、まずは自分の話を十分に聞いてほしい。それなのに、さっさと夫から結論を提示されると、自分が理解されていないという気持ちが先に立ち、反発したくなる。そして、しなくてもいい夫婦ゲンカに発展する。実はこの構図、子供が母親に反発する時と似ている。受験期の家庭では、子供は母親に不満を抱き、母親は夫に不満を抱く関係が生まれやすいのだ。
「コミュニケーションの悪循環を解消するには、相手が子供でも妻でも夫でも、まず話し手の言葉を聞き、そのまま繰り返すこと。リフレインは相手のイライラを落ち着かせるのに、とても効果があります」(大石さん)
「そうなの、つらいのね」「大変だよね」と、相手の言葉を繰り返すだけで、話し手は自分を受け入れ、理解してもらえたという気になり、安心する。その上で、聞き手は「こういう方法もある」「あんな方法もある」と、複数の方向性を提示する。そうすれば、意思決定権を話し手にゆだねることになるので、反発心がやわらぎ、アドバイスが素直に聞きいれてもらいやすくなる。
それでも不安が消えない場合は、どうしたらいいのか。 今回話を聞いた全員が、「次々と新しく課題に取り組むより、基礎問題を徹底して復習させること。出遅れている子供ほど復習が足りない」と口を揃える。子供に自信を持たせるには、達成感を味わわせることが早道だ。慣れ親しんでいる基礎問題を復習すると、分かる部分が多いので自信を取り戻しやすい。一方で、曖昧に覚えている部分が明確になり、これからの期間にやるべきことが見えてくる。
●何のために受験するか
それから、何のために中学受験に臨むのか、もう一度、親子で話し合うことも大切だ。
中学受験は本来、子供の可能性を広げるために受けるもの。ところが、受験が目前になると、第1志望への合格が最大の目的にすり替わってしまうことがある。「中学受験はゴールではない。希望の中学に合格できなくても、高校、大学受験で取り返すことはできる。中学受験がすべてと思っていると、受験で燃え尽きてしまい、入学してから、ついていけなくなる」(和田秀樹さん)第1志望を落ちた時の挫折感も大きく、高校、大学受験まで負け犬感を引きずることがある。これを避けるには、第2、第3志望も慎重に決めること。それらの学校も第1志望に劣らず、子供に合っていることを、親が前向きに説明することだ。
「第1志望以外は価値がないように親が考えていると、子供もそう思いこんでしまう。そして第2志望に行く自分はダメな人間だと劣等感を抱くことになる。また、安易に第2、第3志望を決めると、最悪の場合、学校と子供のミスマッチから、入学後に転校という事態もありうる。必ず学校に足を運び、校風や教育方針を確かめてください」(四谷大塚・和田さん)
大人びてきたとはいえ、中学受験に臨むのは、12歳の子供なのだ。高校や大学の受験生より、ずっと親の影響力は大きい。和田秀樹さんは「中学受験は親で決まる」とまで言い切る。それゆえ忘れてはならないのが「親のサポートは不可欠だが、主役は子供だ」ということ。
◆「言ってはいけない」NG言葉
「このままじゃ、どこにも受からないわよ」
「いくらお金をかけたと思っているんだ」
「本当にそんなレベルの高い(低い)ところを受けて大丈夫なの」
「遊んでいないで、勉強しなさい」
「○○ちゃんもがんばっているんだから」
「ここまでやってきたのに、もったいない」
「イヤならやめてもいいのよ」
◆「言ってあげたい」OK言葉
「がんばってるね」「よくやったね」 些細なことでも、伸びたところを見つけ、こまめに具体的にほめる
「君ががんばっていることが、お父さん(お母さん)はうれしい」
応援している気持ちをはっきりと言葉で伝える
子どもの言動に反射的に言い返さない。一呼吸おいて、冷静に話しかける
「できないところが今のうちに分かってよかったね。本番までがんばろう」
模試の成績が悪くても責めない。前向きな言葉をかける
(参考資料:『後悔しない中学受験』〈中曽根陽子&ワイワイネット/晶文社出版〉)
◆こんな行動が受験直前のストレスサイン
相手の話を落ち着いて聞くことができない
自信がない。自分を好きではない
生活習慣が乱れてきたイライラが続き、家族にキレやすい
自分が今、何をすべきか考えられない
他人への思いやりに欠ける
指示や命令がないと動けない
失敗を恐れて躊躇することが多くなった
都合の良いことばかりを言う
都合が悪くなると嘘を言う
☆チェックから分かる子どもの不満
(親が以下の行為をしているために、子どものストレスがたまっている可能性がある。)
子どもとの会話が不足している
子どもをほめたり、努力や成果を認める機会が少ない
子どもに判断を任せず、親が口や手を出しすぎている
模試の結果だけを見て、瞬時にどなったり、叱っている
「受験にどう臨むか」を子どもに考えさせたり、問いかける機会が少ない
「なぜそうしたのか」「どうしたいのか」という、子どもなりの理由や希望を聞く機会が少ない
大人の指示や命令に無理に従わせている
頭ごなしに叱ることが多い
トラブルが起きたとき、事実を検証せず、子どもの言い分だけを鵜呑みにしている
子どものペースを無視して会話を進めている
(参考資料:『子どもの能力を引き出す親と教師のためのやさしいコーチング』〈大石良子/草思社〉)
教育情報
東京大学 学部・大学院卒業生の進路状況・・・2割程度が不明
(東京大学 ホームページより)
平成17年度の学部卒業者及び大学院修士・博士課程修了者の就職状況集計結果及び概況は次のとおり。(調査基準日は、平成18年5月1日現在)
1.平成17年度学部卒業者及び大学院修士・博士課程修了者の就職状況集計結果
(1)学部卒業者及び大学院修士・博士課程修了者のうち、就職希望者数、就職者数及び非就職者数とその内訳を、学部別、研究科別にそれぞれを表1として集計。
(2)産業別の就職者数を学部卒業者と大学院(修士課程・博士課程)修了者とに区分し、表2「産業別就職者数(平成17年度)」(平成16年度分附記)として集計。(産業区分は、「学校基本調査」の職業分類項目によっている。)表2に示された数字を、学部別、研究科別にそれぞれ表3として集計。
(3)過去10年(平成8年度~平成17年度)の就職状況(卒業・修了者数、就職希望者数、就職者数及び非就職者数)の推移を、表4として集計するとともにグラフで表示。
(4)産業区分を「学校基本調査」の職業分類項目によらずに集計していた平成15年度までの産業別就職者数の推移(過去5年)を、参考までに表5として掲示。
2.平成17年度学部卒業者及び大学院修了者の就職状況概況
平成17年度学部卒業者数は、3,298 人、そのうち就職希望者は、1,212 人(36.7%)、就職者数は1,069人(32.4%)で、就職を希望した者の88.2%が就職している。
非就職者2,229人(67.6%)の大半が大学院進学者(1,746人)で、卒業者数に占める大学院進学者数の割合は、52.9%と就職率(32.4%)を上回っており、この傾向は、平成9年度から引き続いている。
なお、非就職者のうち、臨床研修医(予定を含む)は91人、翌年の受験等(公務員試験、司法試験、その他の資格試験等)を目指している者は195人(卒業生数に対する割合は、5.9%)である。
大学院修士課程修了者数は、3,003人で、そのうち就職希望者は、1,589 人(52.9%)、就職者数は、1,585 人(52.8%)で、就職を希望した者の99.7%が就職している。
非就職者数は、1,418人(47.2%)。非就職者のうち大学院博士課程への進学者は984人(修了者数の32.8%、非就職者に対する割合は69.4%)である。
大学院博士課程修了者は、1,547 人で、そのうち就職希望者は659 人(42.6%)、就職者数は、631人(40.8%)で、就職を希望した者の95.8%が就職している。
非就職者数は916人(59.2%)で、日本学術振興会の特別研究員等も非就職者数としてカウントしてある。
【関連データ】
下記のデータは、学内広報9月13日号(NO.1342)
( http://www.u-tokyo.ac.jp/gen03/kouhou/1342/5.html
)をご参照ください。
http://www.careersupport.adm.u-tokyo.ac.jp/info9.html
国家と教育
(毎日新聞 12月7日 こころの世紀)
何か変だなと思っていた。高校生の履修単位不足なるものが話題になっていた時である。今年の10月末頃から始まり、11月いっぱいまで新聞が大騒ぎしていた。私が何に違和感を持ったかというと、カリキュラムの編成についての文科省の指導要領というものはあっても法令ではないと思ったからである。そうでなければ、教え子の卒業にかかわる問題の放置を教育現場の人々が何年にもわたって続けるはずがない。指導要領はある種の模範で、細部は現場に任されているはず、特に私学の場合はそうだろうと思っていた。現に東京私立中学高等学校協会長が、そのような意見を述べている。私も調べてみたら指導要領は「告示」で、その改訂などは「事務次官通知」に過ぎない。告示がどこまで現場の裁量権を制約するかについては既に長い法廷論争があり、1976年の最高裁判決で「国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請される」という判断も出ている。そもそも文科省の役人たち自身が指導要領の現場解釈について5年も前から気づいていたというのに何でこの時期になってこれを持ち出したのかと疑うべきだろう。
マスコミが大騒ぎしているうちに叙勲を辞退するという元校長たちが次々現れ、茨城県では現職校長が自殺するという事件も起きた。日本のマスコミというのはなぜこうまで「おカミ」に弱いのだろう。一部から左翼呼ばわりされている数紙だけでもいいから、この動きを愛国心教育(教育基本法の改定)と絡んだ文科省官僚たちの恫喝(どうかつ)の一部であることを暴いて欲しかった。
一方、今年の後半は例年になく「いじめ自殺」の問題が紙面をにぎわした。愛媛、北海道、福岡と続いて、福岡筑前町の中学2年生の自殺の頃がちょうど10月中旬、履修単位不足問題が旬の頃だったのだが、これ以後、各紙の報道は次第に高校履修単位の問題から離れる。しかしここでも教師たたき、教育委員会たたきについては変わらない。これら一連の報道に際して、文科省の担当官や大臣の発言は、まるで「葵の紋章」のような扱いを受け、教師、校長、教委批判の道具になっていた。しかし教委が「遺書」を「手紙」と言い続けたり、何年にもわたって「いじめ件数 0」という虚偽を続けてきた理由を作ったのは文科省そのものだ。教育現場は文科省官僚の顔色を読むしかないからうそを重ねるのだ。
いじめられて死ぬ子は、学校には行かなければならないと信じこまされているから生きていけないのだ。そう信じさせているのは親をはじめとする大人たちで、彼らは「公教育」の本質についてほとんど考えていない。ここで「本質」と呼ぶのは、公教育が軍隊と並ぶ「国民国家」の二大支柱ということだ。最初の「国家」フランスはルイ家の領地としてのフランスを否定するところから始まり、ブルボン家をはじめとする国民国家反対勢力の攻撃に備えて軍隊が作られた。国民軍の兵士には共通の国民意識と兵器操作や指揮伝達のための最低限の知識が必要とされる。そこで作られたのが「公教育」であり、「標準フランス語」だ。だから国民国家の成立は領内のオック語やブルトン語を急速に衰退させた。兵士とその妻の数が足りないことがこの頃からのフランス国の悩みで、そのためにそれまで家畜以下の取り扱いを受けてきた孤児たちの待遇が随分と良くなった。「人口を増やすこと」に対するフランス人たちの熱意はこの頃からのものである。
日本でも維新後5年も経たない1872年に学制頒布という形で、皇軍兵士養成の制度が作られた。そういうわけだから公教育とはもともと官僚支配が最も厳しく適用される領域なのである。日本の場合、1945年の敗戦を機に「軍隊を廃する」という大冒険に踏み出したわけだが、公教育の方は戦争遂行のための40年体制(国家総動員体制)は残したままで、マスコミの姿勢に見られるように人々は決してこれを怪しまない。
日本の社会にはさまざまなところに「一億総動員体制」の残りかすが見られるが、それは偶然そうなったわけでも国民がそう望んだからでもない。「戦う日本」のリーダー役を務めた一人の官僚とその徒党たちの意図による。この元官僚は「満州国は私が作った」と言ったそうで、戦時内閣の商工大臣を務めながら、不思議なことに早々と巣鴨プリズンから釈放されて政治家になった。当時のアメリカの意向にそって日本軍の再建を目指し、その過程で官僚独裁制の温存に努めた。彼は作ったが壊れた満州国への夢を戦後日本に実現させたのだ。今の私たちは、この人、岸信介の孫を首相に据えている。その孫は祖父の信奉者であるというから、彼が「愛国心教育」に熱心であることの意味は重い。
京都座会による提言 教育の自由化推進を
(全私学新聞 12月13日)
作家の堺屋太一氏や上智大学名誉教授の渡部昇一氏らがメンバーの「世界を考える京都座会」は、12月11日、東京都内で記者会見を行い、「教育再生への緊急提言」を発表した。
緊急提言は、学校教育が根底から揺らいでいる中で、官僚統制の画一的な教育から脱却し、抜本的な教育の自由化・分権化を求めたもので、現在の「いじめ問題」については、欠点をなくして(嫌なことを強いる)、長所を抑える教育から、長所や個性を積極的に伸ばす教育への転換などで克服できると
し、義務教育を4年間で修了とし、その後は、サッカーや野球、英語といった生徒の得意分野を伸ばすことに大きな比重を置いた中等教育の展開を提言している。
またいわゆる「未履修問題」に関しては、文部科学省の教科の選定、教育内容の枠決めは参考程度に受け止め、各学校はその参考と自校のカリキュラムの差を公表することにとどめるべきだとしている。未履修問題が全国に拡大していることについては現実に合わない制度を文部科学省が強制しているからで、一元的強制以外の何者でもないことを文科省は直視すべきだとした。
さらにいじめ問題や未履修問題をきっかけに文科省が強圧的な姿勢を強めていることへの警戒感や時代認識の欠如なども指摘した。
加えて政府の教育再生会議に関しては、枝葉の議論に終始しており、結局、官僚の作文による中央集権的なことでまとめ上げられるとし、厳しくそのあり方を批判した。
教育の自由化では学校設立の自由(塾も学校として認める)、学校の選択の自由化(教育バウチャーの導入)、教員任用の自由化、教育内容の自由化を求めており、中学校以降では奨学金の充実、寄付金の税制上の優遇措置などを求めている。教育バウチャー制度の導入が進めば、公私立学校の区別はなくなり、その区分は重要ではなくなるとした。また教育の自由化の下では、教育サービスの提供者(学校・教師)には競争原理を働かせて、一方、教育サービスの消費者(生徒等・保護者)には徹底した学校選択の自由等を保障すべきだと提言している。
履修単位不足問題 私学は自主性、独自性で社会に貢献
(全私学新聞 12月23日)
臨時国会が12月19日、4日間の会期延長の末、閉会した。安倍政権発足後初の国会論戦では「教育基本法の改正」と並んで、「いじめ問題」「高校必修教科科目の未履修問題」「タウンミーティングでのやらせ問題」が大きな焦点となった。このうち未履修問題では、多くの県で私立高校も厳しく指弾され、一部の県では補助金の削減すら取りざたされている。また中には査察に訪れた県私学所管課職員が携帯電話で教育委員会と連絡を取り合い、細かな指示をしたというケースもあったようだ。つまり公立学校と同じことが求められた。
しかし公教育の中で私学の役割は、果たして公立と同じようにすることなのだろうか。私立学校の生命線はもちろん「自主性」「独白性」。公立高校と同じなら、私学の存在意義はない。私立学校の創設者は既存の教育に飽き足りず学校を立ち上げた。私学教育はこれまで光の当たらなかった分野や人々のための教育、新しい方法による教育の開発・実践を通じて社会に貢献してきた。女子教育、帰国子女教育しかり、中高一貫教育もそうした私学の試行錯誤の中から生まれたもので、実験・試行、言い換えれば特色ある教育の創造を通じて教育の活性化に貢献してきた。
また未履修校については、特別補習をして修めるべき内容を一定の基準で学習するよう求められているが、生涯学習時代を迎えている現在、高校の3年間にこだわる必要はないのではないか。いつでも学び直せる環境づくりこそが大切で、また生徒の長所伸張がもっと配慮された柔軟なカリキュラム編成があっていいのではないか。小中一貫、中高一貫、高大連携の推進、新しい教育基本法から義務教育の9年間という規定がなくなったことは、学校制度の柔軟化(学習進度の速い子供は早く修了、遅い子供はじっくりと学習)を進めるためのものではないのだろうか。
帰国子女、学習意欲を失った子など生徒が多様化する中で、いまこそ生徒一人ひとりを見つめた柔軟なカリキュラム編成が求められているのではないだろうか。
ところで先月、全私学新聞に読者の一人から未履修問題に対する意見が寄せられた。ここで要約を紹介し、多くの方にこの未履修問題を考える材料として頂きたい。
◇
今般の未履修問題については、私学にも追及の手が波及し、それぞれの教育現場では深刻な問題として受け止められている。そもそも学習指導要領が法律であるか否かについて見解に統一性がないことはご承知のとおりだが、今般の文部科学省及び各県私学担当部局の対応については、私学を公立と同一視し、なし崩し的にコントロールを強化しようとする意図が見られ、これに強い危機感を持つ。この流れは、報道各社の姿勢にも表れている。新聞等は学習指導要領の未熟な解釈により、まず初めに授業時数ありきとの論調が目立ち、本来持つ学習指導要領の意義を曲解している。また文部科学省、各県私学担当も、これを機会に私学の特色ある教育の中身に立ち入ってコントロールを強化しようとする意図も感じられ、このまま放置すれば、私学の特色ある教育の権利を大幅に奪われるのではないかと危惧している。
無論、学習指導要領には、ある程度法律に準じた拘束力があることは認められるし、必修科目として課された以上、全く世界史の授業を行わないなどという態度は、公に準じる私立学校といえども、批判を受けることは当然であろう。しかしもし私学が公立学校と同列に県当局・県教育委員会のコントロール下に置かれた場合、法律で保証されている私学の独自性は、どこで担保されるのか。もしも県当局や教育委員会がカリキュラムの中身にまで立ち入ってくるとすれば、例えば数学Ⅰの単位の中で、先行して数学ⅡやBを学習させることは違法と解釈されるかもしれない。世界史の授業を早めに完了して、残余の時間で日本史の領域に入ることが違法なのだろうか。情報の学習に関連させて、数学の内容に踏み込むことは違法なのだろうか。
教育委員会が所管の公立学校のカリキュラムに対してものをいうことは問題ないと思うが、私学は違うと思う。県の監督部局は私学に対しては、あくまで施設・設備、教育課程その他の届け出書類その他を管理監督する部署であって、教育の中身を決定するのは理事会であり、各学校であるはずである。
その他
名言・迷言・冥言
(ビートたけし 友達より)
困った時、助けてくれたり
自分の事のように心配して
相談に乗ってくれる
そんな友人が欲しい
馬鹿野郎、
友達が欲しかったら
困った時助けてやり
相談に乗り
心配してやる事だ
そして相手に何も期待しないこと
それが友人を作る秘訣だ
寄稿 出庫数から見る2007年中学入試
(声の教育社 三谷 潤一)
書店営業をしていると、立ち読みをされているお客様が気になる。
迷惑だ、というのではない。ご覧になっている書籍が気になって仕方ないのだ。何が売れているのか、どんな本を手にされているのか、知りたい気持ちを抑えられない。新刊本が平積みされていれば、自分から手に取ってもみる。最近増えている受験指南書、受験体験談集。大抵は不安な親の心理を巧みに突くネーミングの妙が目立つくらいで、ぱらぱらっとめくれば内容の見当はつく。お客様が手にされているのが自分の会社の出版物なら無関心を装いながら、「お買い上げ下さいね」と祈る。競合会社のものと両方、手にされていようものなら、心中穏やかではない。「買って下さい、買って下さい、買って下さい、買え買え買え買え…」と口には出さずに念じ続ける。変なオーラを背後で察知されるようで購入せずに逃げていく方が少なくない。
今年の前半は、ビジネス誌の出す教育関連雑誌がよく立ち読みされていた。最近は『入りやすくてお得な学校』を熱心にご覧になっている方をお見かけする。きっと、こどもの模試の結果が思わしくなかったり、もっと確実な滑り止め校を探すよう勧められたりしているんだろうなあ、と勝手に想像する。来春入試は受験生にとって大激戦になる、といわれている。当事者にすれば、不安を掻き立てられるのはもううんざり、というのが本音だろう。入試が目前に迫っていて心中穏やかではいられない時期だ。もう余計な情報は聞きたくない、という方には顰蹙を買いかねないが、今年も小社発行の学校別問題集の出庫状況比較についてご報告申し上げます。
発行していない学校についてはわからないし、例年動きの良い学校(たとえば香蘭女学校)は各書店が多めに注文をくれていたりもするので、その影響というのも考えられる。また、学校で問題と解説を配布したり、ホームページで公開したりしていれば売上げは下がる。小社が市場を独占しているわけではないので、収録についての変更が響く場合もある。一概に相関関係があるとは言い難いが、全くないということもあるまい。何らかの参考にして下されば幸いである。
なお、小社発行の学校別問題集についての品切れ品薄校はHPで随時更新中です。
http://www.koenokyoikusha.co.jp/