

NO.118
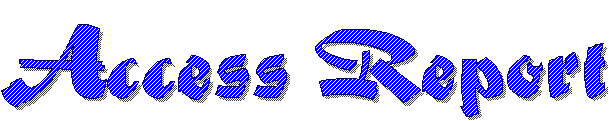
2003年 12月 5日
アクセス教育情報センター
目次
|
学校情報 |
学校情報 | 教育情報 | 教育情報 | その他 |
| 那須海城中 | 渋谷幕張
公開模試情報 |
県千葉を中高一貫校に | 私立高校の学費滞納 | 自衛隊イラク派遣 |
学校情報
那須海城中 冬の体験入寮
夏の体験入寮には約130組、秋の体験入寮には約40組が参加。
日時 平成15年12月6日(土)・12月7日(日) <1泊2日>
会場 那須高原海城中学校・高等学校
対象 中学校3年生、小学校6年生男子
費用 1泊2日 生徒・保護者 お一人3,000円 <税込>
交通 東京駅・新白河液より無料送迎バスをご用意しています。
自家用車で来校していただいても構いません。
寮生活を実感。在校生たちに話が聞ける。授業参観できる。
「寮生活を実体験したい」というご要望にお応えして、12月に中学校3年生、小学校6年生を対象とした1泊2日の体験入寮を行います。寮での過ごし方を体験し、また、在校生に話を聞いたり授業参観することで本校をより深く理解していただけます。
また、教育相談も兼ねたAO入試(アドミッション・オフィス)を実施します〈特別入試〉。
ぜひ、親子での参加を特にお薦めします。もちろん、お一人での参加も可能です。
集合時間等、詳しいスケジュールは申込終了後、改めてご連絡します。
保護者の方も寮に宿泊できます。(生徒とは別の部屋を用意)
ご家族、お友達との参加も承っています。
参加費は、当日現地にて徴収させていただきます。
http://www.nasukaijo.ed.jp/index.html
学習院女子 学校説明会報告(03年11月22日)
1. 基本理念、方針について 中等科科長 稲田先生
4月から科長に。
1877年神田に華族学校として創立。当時の校門が現在の正門として残っている。
1885年に昭憲皇太后により、女子にも独自の教育をという趣旨で、四谷に華族女学校を創設。
その後学習院と合併し学習院女子部に。
さらに学習院と分離し女子学習院となる。
1947年に宮内省の所管を離れ、私立の学習院女子中等科・高等科となる。
その時代にふさわしい女性としての知性、品格を養う。
「金剛石も磨かざれば珠の光はそはらさむ」の言葉を原点として、金剛石の原石である生徒一人一人の能力を磨き上げる。
近代化を目指す日本の女子教育の先頭を走り、女子を中心とした独自の教育を行ってきた。
今も生徒一人一人が原石であることは同じ。生徒には原石であることの誇りと自信を持つように話している。
全人教育を目標に、社会に貢献できる女性を育成する。
21世紀は女性の活躍の場が広がる。今こそオールラウンドな女性が求められている。
学習活動、クラブ、委員会、学校行事等を通しての先生と生徒、生徒同士の人格的なふれ合いの中で成長していく。
学習院大学を70~75%が希望。他大学を25~30%が希望。
他大学進学希望が徐々に増えている。
生徒が目指す道に対応できるように、高3では選択科目を多く配置している。
高2で文系、理系分けを行う。
国際化教育も早い時期から行ってきた。留学生の受け入れは30数年になる。帰国生の受け入れも25年近くになる。
高等科では選択科目でドイツ語かフランス語を選ぶことができる。
英語は少人数で習熟度別授業を行うなど外国語教育に力を入れている。
日本人として日本語、日本の文化も大切にして欲しい。
古典基礎、表現では独自の教科書を使っている。
日頃から美しい言葉を使えるように指導している。
生徒に対しても敬語を使い、大人としてLadyとして接する。
卒業生には国際的に活躍している人や様々な分野で活躍している人がいる。
流行に流されない見識と批判精神を持って欲しい。
地味でも堅実で、正直と思いやりの精神を持つ人になって欲しい。
21世紀を背負う立派な大人に育てることが教育目標。
今の若者をみていると日本の将来が危ぶまれる。
子供たちを自立させ、自分の頭で考え決心して行動することを身につけさせる。
中高の6年間は人間の成長にとって大切な時期。自分とは何かを見つけ自立し、社会に貢献できる人になる基礎作りの時期。その時期を都心にありながら広大なキャンパスと四季折々の自然の中で過ごすことができる。
学習院女子では生徒の自主性を尊重し干渉しすぎないように配慮している。
 グランドとソフトボール部
グランドとソフトボール部
2. 学校生活について 生徒課長 香川先生
学習院女子の制服はセーラー服の源流になったもの。
ごきげんようで登校。ごきげんようは伝統の挨拶。入学当初はとまどうがすぐに慣れる。
学校生活においては、細かな規則で縛るのではなく、それぞれの個性を生かして自立できる女性を育てるように配慮している。
委員会活動では学年を越えて活動。
クラブ活動の参加は任意。03年度は中学生601名中566名が何れかのクラブに所属。高校生は571名中496名が所属。高3の1学期まで活動している。
人数の多いクラブはダンス部、テニス部、バトミントン部、アンサンブル部、演劇部、華道部など。
主な行事
4月に毎年クラス替え。新しいメンバーになる。
球技会・・クラスの団結が生まれる。
4月中に担任(主幹)と生徒の個人面談を行う。
中1交流教室・・新入生の友達作りを目的とした宿泊行事。2泊3日。
中3修学旅行・・山陽方面へ平和学習を目的として。
イートンサマースクール・・夏休み中3週間、イートン校の寮に宿泊。中3、高2、高3の希望者対象。楽しくて帰りたくないという雰囲気。
中2臨海学校・・沼津にて。
運動会・・学年対抗やクラス対抗の競技がある。
中1お茶会・・道徳の授業として作法を学ぶ。
百人一首大会
送別学芸会・・高3の卒業生を送る会。
学年担任制(共同担任制)
5人がチームとなって5クラスの生徒を担当する。
原則として3年間持ち上がり。
生徒にもできるだけ敬語を使うように心がけている。
3. 入試・教育課程について 教務課長 松尾先生
1) 04年入試に関して(一般生入試)
2月1日 女子約120名 4科 面接
親元(父母または親権者の住居)からの通学が条件。(祖父母の住居からの通学は不可)
通学範囲の制限はない。70%が都内、10%が千葉、10%が埼玉、7%が神奈川。
報告者・健康の記録の提出を廃止。通知表のコピーに。
通知表のない学校は6年生1・2学期の出席状況を校長公印で証明できるものを。
二期制の学校は一期の成績表のコピーと12月までの出席状況を提出。
成績表に数値評価のない学校はそのままのコピーで可。
国語50分、算数50分、社会30分、理科30分。
03年入試から社会、理科の時間が合わせて60分から30分ずつに。
各教科の学習のポイント・・後述。
2月1日の午後に面接。面接は受験生と保護者1名。
面接は受験生本人、保護者の方に一度お会いしたいということ。
手続時納入金が入学金(300,000円)のみに。手続き後に辞退されても入学金の返金はない。
合否は4科の総合点(320点満点)で判定。足切りはない。
ボーダーのところでは面接で判断。
秋篠宮の第一女子眞子内親王が04年4月に学習院初等科から進学して来られるが、中等科入試の判定方法に関して例年と変わるところはない。
合格発表は掲示による発表のみ。
04年入試ではサンデーショックの関係で補欠者数を多めに出す予定。例年は20数名を発表しているが、前回のサンデーショックの時は40名発表し全員繰り上がる。
繰り上げは補欠順位に従って連絡先に電話で連絡。
手続き後に入学辞退される場合は速やかに連絡を。
寄付金(1口10万円、3口以上)は任意。入学手続き完了後に法人の方から寄付のお願いがある。
2) 03年入試結果
一般生入試
募集人数 120
応募者数 236
受験者数 223
合格者数 141
補欠者数 30
補欠繰上 20
入学者数 128
受験生平均 国語 算数 社会 理科 合計
53.3 58.9 25.7 38.2 176.1
(100) (100) (60) (60) (320)
合格者最低 40 21 11 28
合格基準点 170点(320点満点)
3)05年入試に関して(現5年生の入試の時)
2回入試に移行し、一般生入試の募集定員を120名から125名に。帰国生入試の募集定員を20名から15名に。
A 2月1日 女子90名 4科 面接
B 2月3日 女子35名 4科 面接
4) 学習院女子の教育
週5日制は当面考えていない。学習院女子の考えている教育は5日では無理。
中学は02年から新学習指導要領の適用になったが、中1では授業時間を1時間増やしている。
高1までは語学、芸術の一部に選択があるがほぼ共通履修。
高2で文系、理系に別れ基礎科目に時間をかける。
高3は文系、理系の中でさらに進路に合わせた細かい科目選択。
日常の学習をしっかりやっていれば塾、予備校は不要。
補習は各教科が必要に応じて行っている。
他大受験を目指す生徒の中にはは必要に応じて予備校に行っている生徒もいるが、学校の授業で大学受験の基礎学力は充分つける。
クラス編成は一般生入試からの生徒、帰国生入試からの生徒、初等科からの生徒を混合して1クラス40名前後の5クラス編成。
学習院大学、学習院女子大への進学希望が70%、他大学進学希望が30%の割合。
学習院大学、学習院女子大からの就職は順調。特に学習院女子出身者は女子大の中では飛び抜けてよい。学習院女子に対する社会的信用の高さではないか。
4. 04年度中等科入学試験に向けて(配布資料より)
〈国語〉
国語は、新聞や本を読み、人の話を聞き、自分の意見を述べるという日常生活の根幹に関わる科目です。従って国語の勉強もこの日常生活と離れて存在するものではありません。日常生活に根ざした国語の力を試すため、出題は毎年、比較的長い文章を読み、自分の言葉で答えるという形式をとっています。具体的には、次のような基礎学カづくりを心がけて下さい。
・普段の生活の中で正しい言葉遣いを心掛ける。
・毎日少しでもよいから時間を設け、幅広い文章に接する。
・漢字の読み書き、語句の意味調ベ、など常に国語辞典を用いて確かめる。
〈算数〉
入学試験では、計算力・論理的思考力・図形に対する洞察力・数学的直感力・それらを的確に表現する力、を見る問題を出題します。採点に際しては答えだけでなく途中の考え方や式も重視します。普段から次のような習慣を付けておくと良いでしょう。
・丁寧な字でしっかり書く。
・途中の式や計算を必ず書く。
・表や図を用いてわかりやすく表現する。
・図形は、三角定規・コンパスを用いて丁寧に描く。
〈理科〉
理科では、日常の場で出会った現象に「何だろう」「どうして」と考えてほしいと望んでいます。もちろん、小学校の授業をしっかりやってくることは必要ですが、それ以上の知識は求めていません。与えられた条件から考える問題でも、小学校で習う範囲内でどう考えるかを評価しています。
近年、説明をもとめた問題で、「だれが」「何が」といった主語のない文が多いのが気になります。主語をきちんと書く習慣をつけてほしいと思います。
〈社会〉
例年、社会科は基本的な事項を問う問題を多く出題しています。
人名・地名・年号といったジグソーパズルのピースを組み上げるためには「なぜ?どうして?」を常に意識することが大切です。事典を調べてみたり、地図帳を開いてみることで疑問がとけることもあると思います。
時事的な問題もよく出題されます。日頃からニュースや新聞に親しんでおきましょう。家族で交わす会話は、とりわけ深く心に残ります。日常生活そのものが、社会の最も効率のよい学習の場です。
〈作文〉・・・帰国生入試
作文は、作文A・作文Bという二つの課題があります。
作文Aは、表現力や創造力、豊かな感受性が求められます。課題に対し、海外での経験や日頃の読書経験などを生かして、自分の考えや思いを自由な発想で伸び伸びと表現して下さい。言語は最も得意とする言語を使用します。
作文Bは、論埋的に考え、説明するカが求められます。課題に対し、相手に正確に伝えることができるよう、客観的な視点を持って書くことが大切です。言語は海外で習得した言語を使用します。
5. その他
図書館は独立した建物で1階を中高が、2階3階を女子大が使用。高校生は女子大の図書館も使用できる。
1階には37000冊が開架に。古い蔵書は戦災で焼けてしまいあまり残っていない。
年間の貸出冊数は7000~8000冊。
平日は8:30~16:20(土曜は15:00)の間開館。
グループ調べが出来る部屋が2ヶ所閲覧室の奥に用意されている。
 閲覧室
閲覧室
各学年5クラス。東西南北中のクラス名。
皇族の関係者も一般の生徒と扱いは同じだが在学中は警備が厳しくなる。
今年は一般説明会を2回実施。2回目も体育館の後までほぼ埋まる。
帰国生説明会では参加者が少ないので学内見学がゆっくり出来る。
(報告 A.A)
http://www.gakushuin.ac.jp/girl/
女子学院 学校説明会報告(03年11月18日)
木枯らしの吹き始めた11月18日、朝8:00。女子学院中学高等学校の講堂は、1階前方の生徒席を残して、2階まで満席となった。本年度最終となる第3回の説明会の開始は8:10分。パイプオルガンの演奏とともに、中学1年生徒が入場。さらに田中弘志院長が壇上に上がり、礼拝の開始となる。礼拝の聖書講読は、「マタイによる福音書・第18章21~35節」から。イエスが、ペテロの「わたしに対する罪を犯した兄弟を何回赦すべきか」という問いに対して、次のようなたとえばなしをする。「主君に莫大な借金を帳消しにしてもらった男が、わずかな貸しのある男を見つけて、首を絞め、返済できるまで投獄してしまう。周囲の者は心を痛める。話を聞いた主君は怒り、男の借金の帳消しを覆し、投獄する。」昨今の不良債権を抱え込んだ銀行と中小企業の関係を思わせるこの内容を、院長は貨幣価値などにも触れつつ、生徒自分自身のあり方や、話を第三者的な立場ではなく自らの問題として捉えることを諭す。論理が明快で、なおかつ親しみやすい説教であった。その後、村瀬教務主事が司会に立ち、「なぜ、早朝からの説明会なのか」という点に触れる。教育の基本姿勢としての礼拝を見てもらうためと、朝の通学で、子女がどのような混雑度合いの電車に乗るか、また、本校の生徒がどのようなようすで通学しているかを見てもらうため、という内容。約10分の休憩後、説明会開始。以下、その概要を記す。
1.「女子学院の教育」田中弘志院長
(1) キリスト教精神に基づく教育
キリスト教主義だが、生徒の中での信仰者はわずか。専任教員61名、専任職員10名の中での信仰者は40%程度。それでも、日本の総人口に対する信仰者の割合1%にくらべると、多い。
①信仰を通して育まれる人間観「主を畏れることは知恵の初め」
何かを学び、生きていくうえで、「生かされていることを知ること」が大切。それは、超越者(創造主)に造られたもの(被造物)としての限界、弱さを知ることであり、人間としての謙虚さにつながっていく。とはいえ、人間は決してつまらない存在なのではなく、大切な一個の人格を備えている。神の前では平等。この考えを生活の中にあてはめていく。自分自身も、無力だが、大切な存在。そうであれば、周りの人も同じなのであり、決して粗末にはできない。生徒は一人一人が平等で大切な存在である。
②毎朝の礼拝が学校生活の中心
講堂を使う礼拝は、ふだんは中学生全体が火曜と木曜、高校生全体が月曜・水曜・木曜に行われる。講堂を使わないときは、教室でのホームルーム礼拝を行う。教室では、生徒が交代で司会をする。時には教師が司会をすることもある。毎日の礼拝の時間に自分を見つめることが、生き方を考えることにつながる。講堂礼拝では、教職員も列席する。神の前では生徒も教職員も同列。また、週1回の聖書の時間は、自分の行動の規範、いわば行動の座標軸を持つ姿勢をはぐくむ。
③一人一人をかけがえのない人格として
「自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい」自分を愛するとは、決してエゴイズムなのではなく、自分のあり方を大切にして粗末しないこと。
(2) 生きる力をはぐくむ
抽象的なことばになりがちな「生きる力」だが、勉強による知識のみではなくは生活力のことだと考えている。「学び」は多く側面を持っている。たとえば、教科外活動、家庭での役割、友人との交流やつながりからも学ぶことは多い。
①学びの基本=基礎学力を身につける
・実験・観察・体験
覚えるだけではない、学ぶ喜びを持続させるのが学校の責任。座学のみではなく、観察、実験、体験に重点を置く。
・文章を書く作業
国語だけではなく、社会や聖書などの授業でも積極的に書くことをさせる。読み、聞き、体験したことと、自分自身との関わりを考え、書く。そこには必ず「考える」作業が伴う。実践例としては、夏の宿題としての戦争体験の聞き書き、広島の旅行や文芸作品の感想文など。
②バランスのとれた人間形成
・教科活動と教科外活動
この場合のバランスとは、知育と体育、心と体、人間関係、自分と社会など。現在やっていることと、全体との関連を考える訓練が必要。生徒たちは、教科活動に対して教科外活動への積極的な取り組みも行う。教科外活動には、ホームルーム、生徒会、クラブ活動、委員会、学校行事等があるが、中でも生徒たちのクラブ活動に注ぐ情熱は特筆すべきものがある。クラブ活動への参加は基本的に自由だが、参加率が高い(高校1・2年でさえ88%)。中にはかけ班(女子学院では、クラブのことを部とは言わず班と称する)する強者も。また、ボランティア活動に参加する生徒も多い。
中学1年の遠足は、今年は昭和記念公園(立川市)へ行ったが、その際、理科科から事前にわたされていた植物のプリントをもとに、事典を検索、各自が「My図鑑作り」をして臨み、自然の草花を観賞していた。
授業では、予習復習は基本で、宿題も大量に出る。また、生徒たちは熱心にクラブ活動に打ちこむので、かなり忙しい生活になる。だから、入学後はできるだけ塾には行かせないでほしい。塾に行っている生徒の割合は少な目。生徒会の行ったアンケートによれば、中学生で19%、高校生は2年生の秋まではクラブ活動に忙しいので通塾率は低い。ただ、高校2年の秋を過ぎると皆勉強に切り替わる。
・家庭での役割
家庭でお風呂掃除などの役割を決めて実践することは、中学低学年で奨励している。役目を担うことでの達成感が大切。
・他者の尊重・受容
女子学院のイメージは、一般に「明るく、活発」なのだが、現実には引っ込み思案だったり内向的な子供もいる。それを変容させるということなのではなく、生徒それぞれが、さまざまな個性の人間がいることを前提として、お互いを認め、受容しあう、本来の豊かな心を育んでいくことが大切だ。
(3) 自主性、自発性を伸ばす教育
①「自由」の中でこそ自主性は育つ
女子学院の校風は言うまでもなく「自由」で、目に見えるかたちだけでも、「制服がないこと」と「校則が四つしかないこと」が挙げられる。教員側のスタンスとしては、まず、やらせてみるというのがある。たとえば、学校行事を生徒自らが企画、運営、実行するわけだが、その際も「ダメ」「ストップ」と言わない姿勢をとる。そのとき、生徒自身が判断し挑戦する姿勢にこそ、独創性が生まれる芽が生ずる。失敗することも多い。だが、逆に学ぶことはもっと多い。まずやってみようとする意欲が集団の中に育まれるとき、easy goingな姿勢ではおいて行かれるというマイナスにも気づける。
先日の朝日新聞の「声」という投書欄に、携帯電話の使い方に関する投書があったが、女子学院の生徒ではないかと思う。本学では確かに携帯電話の持ち込みを受容しているが、教員は適切な使い方を指導するのみである。そんな中、生徒同士による抑止効果が生まれはじめているのも確か。投書はそれを提言するものであったが、実情は、まだ授業中に受信音を鳴らしてしまい、気まずい思いをする者もいる。「自由」の背景には、「厳しい要求」があることを生徒たち自身が感じ始め、確実に成長につながっていると思う。
②背後で支える教師のまなざし
女子学院は「自由」だが、決して「放任」ではない。教師は、一歩退いた位置から見守る。象徴的なのは、クラス日誌。子供同士のやりとりが中心だが、一日のできごとをリレー式に書いていくもので、かなりのボリュームになる。教師は生徒に意見を求められることもあり、時には書き込みで返事をすることも。
高校生になると茶髪に染める生徒などもいて、心配されるむきもいらっしゃるが、入学後2ヶ月めでのアンケートで「自由と聞いていたので心配していたが、事細かに指導されるので安心した」という声を多くの保護者からいただいている。
2.「カリキュラム、学校行事、入学試験について」村瀬きく教務主事
①生徒数と教員数
生徒数は1380名(各学年230名/5クラス)。教員の構成は、専任講師61名、非常勤講師40名。専任職員(事務)10名。1クラスは44~46名での構成。毎年クラス替えを行い、基本的に5人の担任は3年間持ち上がり。教員は学年担任の意識を持っている。
②授業について
週5日制、6時限、50分授業だが、ロングホームルームはこの範疇に入らず、中学生ならば水曜の7、8時限で行っている。土曜日は、授業はないがクラブや委員会活動のため、9:00~16:00までは開校している。授業は、前後期で科目の入れ替えのあるものがある。たとえば、前期・保健で後期・体育など。
③高校新カリキュラム
高校は、新カリキュラムに入った。週30時限授業。旧カリキュラムでは、高校2年より、ホームルームは共通するものの、文理のコースに分かれて学習していた。だが、新カリキュラムでは、高校2年までは全員が同じ科目を履修する。基礎知識の統合や、数学の物理・化学などの理科分野への応用といったのような科目間リンクを生徒に意識させるのがねらいでもあり、また、教育方針である「バランスのとれた人間の育成」の実践でもある。文系も理系も、基礎はきちんと学んでほしい。たとえば、理系の人でも世界史の系統学習を、文系の人でも物理の演習をというように混在させることでの生徒間での触発、ひいては自らの考えを構築できるようになってほしい。高校では、英語は1年、数学は2年からグレード別授業を行う。英語は、5クラスを7つに分ける。演習では、大学入試問題程度の問題を扱う。
④書かせる実践
中学の理科は、すべて特別教室で授業を行う。特に第2分野では、毎時間観察と描写を行わせる。書く・描くことは当然教師の指導が入る。地理などでも、校外学習であればレポート指導が行われ、数学でも、解法をみんなにわからせる書き方を心がけさせる。
⑤総合の学習
ロングホームルームや学校行事を充てる。校外学習を通して課題の研究を行わせる。主なところでは、中学1年6月のオリエンテーション合宿、中学2年7月の御殿場教室、中学3年5月東北旅行、高校1年7月ひろしまの旅、高校3年4月京都・奈良への修学旅行、高校3年7月御殿場での修養会など。なお、ひろしまの旅は自由参加だが、本年は230人中225名が参加。不参加者には、他の体験や研究の課題が出される。それ以外では、中学1年生では千代田区のプールを借りて、3日間の水泳指導が行われる。また、高校2年時に、専門学校(打ち合わせ中)での情報Bの授業を予定している。最新のパソコンに触れさせるため、専門学校の設備を借り受ける。授業内容は検討中だが、高校1年の終わりの春休みか、高校2年の夏休みはじめに実施予定。
⑥保護者会(JG会)
月一回の委員会、5月の総会、6月の教育懇談会(学年ごと)、クラス懇談会は年1~2回、聖書に親しむ会、ボランティア活動、バザーといった活動をする。
⑦進路指導
将来自分が何をしたいのかを決める指導を行う。
中学3年~高校1年時に、卒業生を招いて話を聞く会を開く。招く卒業生は30~40代の年齢層。現在の「学び」が、将来の仕事にどう関わっていくのかを考えさせる機会としている。また、進学準備を目前に控える高校2年時には、大学2~3年生に話を聞く会を開く。進路選択として学部、学科の具体的な現状を把握させる。なお、文系進学者と理系進学者の割合は、年によって異なるが、毎年ほぼ半々ということころ。浪人生も1年で進学先を決めている模様。
⑧中学入試について
通学圏内は、親許から90分以内でお願いしている。突発事項の対処の際に速やかに親とのやりとりができることと、何より彼女らの中学生らしい生活を送ってもらうためということが理由。
⑨本年の試験順序
本年度入試の順序は、国語・理科・算数・社会。
8時30分より試験開始。試験時間は各教科40分間で、それぞれの教科の間の休憩時間が15分間。45分間の昼食後に5名ずつのグループ面接。約8分。面接の時間帯は、当日の朝、プリントにて配布。面接に関しては「女子学院の生徒らしいか」が観点で、合否はあくまで総合点による。内容は、口頭で答えてもらうもの、話し合いをしてもらうもの、時には散乱した衣服をたたんでもらうものなど。先頭を切ってリーダーシップをとる生徒であっても、それに従っている生徒であっても「女子学院らしい生徒と考えている」。なお、報告書は、通学している小学校側にも女子学院を受験することを知ってもらうためのものという位置づけ。
⑩テスト範囲
新課程ではなく、旧課程での出題。あくまで、基礎の上に立った応用で解けるものや日常生活の身の回りを見る目があれば理解できるものという視点での出題。用語など、必要に応じて注釈は加える。
⑪各教科の作問観点・各教科のポイント
・国語……書いてあることを正しく読めるか。
・社会・理科……学んだことを生活にむすびつける視点があるか。そして、それを応用できるか。知識が正確か。
・算数……正しい論理で思考できるか。基礎訓練ができているか。
おしなべれば、基礎的な知識を知っていて、それを正確に出せるか、そして、正しい論理で考える習慣があるかということが大切と言うことになる。
3.「中学校担任から」 小塩めぐみ教諭
数学を担当。担任を持って5年目になる。現在は、中学2年生の担任。授業運営上の観点としては、理解していることがらを共通のことばで表現させること、正しい論理過程をどう楽しませるかということ。学習知識と生活の必要性がどう結びつくかを伝えている。演習に時間をかけ、解答をいかに相手にわからせるかという「書き方」を学ばせる。ゲームや問題づくりのほか、(ポスターの裏と赤い毛糸(?)を利用した手製の二次関数の放物線グラフの模型を提示して)ビジュアルに理解してもらうことにも心を砕いている。なお、学習内容は旧課程の内容も盛り込んだ独自カリキュラムで、中学3年から高校内容を先行学習させる。内容がハードなぶん、復習のミニテスト、宿題の提出、そして、必要に応じた勉強会(補習)を行ってフォロー。学習の中で、他人の考えを知って、認める習慣をつける。そういった意味では、授業は生徒一人一人が作っていくものといえる。
4.「保健室から」甲藤良子養護・保健体育教諭
保健室は、3名のスタッフで、授業時も必ず人員配置できるようにローテーションを組んでいる。
保健体育の授業は、半期ながら、自らの身を守る知識として位置づけになる。中学1年生から「身体・性・心」というテーマで進めていく。また、心的ケアのカウンセリングは35年の歴史を持ち、生徒のみならず保護者のカウンセリングも行っている。保健室は、ちまたでは「オアシス」と呼ばれることが多いが、女子学院では、元気になって教室に帰っていく中継地点、すなわち「ステーション」をイメージしている。
5.「設備、防災、入学時の費用等について」永嶺雄三事務長
(報告者:建物の配置、防災時の対応等についての説明は、省略させて頂きます。同内容が03年9月5日のレポートにあります)
・パイプオルガンを本年夏に設置。
・手続き締め切りは1月24日(土)だが、銀行振り込みは23日(金)となる点に注意してほしい。
・入学後寄付金のお願い。1口10万円で3口以上。
6.質疑応答(報告者:報告にふさわしいいくつかをピックアップしました)
①教員の男女比
それぞれの学年の担任に男性が一人いるが、中1と高2は全員女性。
②海外赴任について
保護者の海外赴任に伴う転居をする場合、一時退学をしてもうらう。復学する場合、編入試験を実施。原則としては必ず編入が可能。国内転居の場合も同じ。インターナショナルスクールに在籍、高校時の同学年学習が困難な場合などは、一学年下に編入する措置をとる。
③留学について
同学年に復学が可能な制度がある。休学の形で、一学年下の復学も可能。留学者は年に5人ほどいる。
④サンデーショックについて
300人ほどの受験者増が見込まれている中、他校進学も勘案して合格者は例年より多めには発表する。面接の終了予定時刻は午後4時。教室は天井から暖房を入れているが、調節可能な衣服で臨んでほしい。なお、受験時の服装は自由であり、面接用に改まった服装である必要はない。着替える場所はないので、着替えは持参しないでほしい。
(参考・・・女子学院広報より)
女子学院は、言うまでもなく、自由および自主性尊重型女子校のフラッグシップ的存在である。その「校風」は桜蔭をはじめとした女子進学各校とのカラー対比がなされる一方、「自主自律尊重」を標榜する女子校のモデルにもなっているように見える。では、その「自由さ」を在校生および保護者がどのようにとらえているのか、「女子学院広報」7月号から引用してみよう。
【服装自由化が問いかけたもの】
○
女子学院は、制服やこまかい規則がなく、生徒の自主性を尊重する自由な校風で知られています。一方、何でも許される派手な学校、どいうイメージを持つ人も多いようです。そこで、女子学院の唱える「自由」の意味を、1934(昭9)年の「制服着用」から1972(昭47)年の「制服自由化」への流れの中で、改めて考えるとともに、お母様方、生徒指導の先生に服装の規定が無いことについて伺ってみました。
「制服着用から服装自由化への経緯」
一、新入生より制服着用(昭9)
政府が学問、思想、文化の強い統制をめざし、思想取締りを強化する時勢に抗しきれず、父兄の意見を聴取した上で決定。それまでは、「モガ」もいるオシャレで自由な学校であった。翌年二・二六事件勃発。
二、物資不足の為、制服廃止(昭18)
これ以降1947(昭22)年のJGバッジが決められるまで、細かい規定は無い。
三、JGバッジおよび生活規則制
学制改革に伴い出来た新制女子学院中学・高校は学級数が増えた為生徒の個別指導が難しくなった。
四、通学服についての制限(昭30)
これは、肌をあらわに出すようなファッションの流行に対処するもので、生徒の身を守ろうとした為のもの。夏のブラウスとスカートの望ましい形を示した。
五、中学一年生への制服着用の義務づけ(昭38)
制服は旧来のようなセーラー服となり、新たに詳細なる服装規定が制定された。
六、服装規定の廃止(昭47)
大島院長(当時)の父兄あての通知状の一部
「いったい服装は個性をもって自分で選びとるものであり、機能に応じた用い方を工夫すべきものであって、中学生、高校生にとってはそのことが一つの教育であると考えます。……学校側としても派手さを競い合う現象が起こることも心配しないでもないが、もしそうなったとしたら、女子学院のこれまでの教育に欠陥があった証拠だから別途策を考える。」
これに対して父兄や生徒達の反応は次のようなものでした。
父兄は…賛成、反対が鮮明なのは少数で、あとの大多数は「式服などについて標準服を指定する」ことなどの条件付賛成が大勢を占めていた。
生徒達は…中一のあるクラスでは黒板に「私服反対」の落書きもあったが全体としては冷静に受け止められた。
「服装自由化」までの主な流れを以上のようにまとめてみました。ここで唱えられた自由とは、女子学院が「神以外の如何なる権威にも屈しない」学校であることを改めて確認するものでした。それは又生徒達が「自由」という権利を六年間でどのようにきずくか、という大きな課題をおわされたことにもなりました。『女子学院の歴史』「目で見る女子学院の歴史』『自己確認の旅』(大島孝著)参考
○「服装の自由」について聖親会にご出席のお母様方と生徒指導の先生に伺いました。
聖親会ご出席のお母様への質問(5月13日実施)
Q.制服についてお答えください。
①今までどおりで良い
理由…気温の調節が出来て衛生的・学校を選択した理由の一つ・自由であっても節度がある・一番わかりやすい自由だから・自律、自立を育てる上で自由がよい。特に華美にならず手頃な値段の服を着ている・JGの「自由な精神」の象徴
②あったほうが良い
理由…登校時の安心のため・ファッションを楽しむのは良いがだんだん派手になる・お金がかかる
③行事の時だけ基準服があると良い
理由…公的・私的のけじめをつける意味で
竹内先生(生徒指導)のお話
服装については多少の注意を払いながら最終的に生徒の自主性に任せていますので生徒指導としては何もしていません。生徒たちは試行錯誤しながら自分に一番合った服装を見つけていっていますね。春に高三の修学旅行について行きましたが皆落ち着いた自分らしい服装をしていました。
服装以外の面でも同じようなことが言えますので、規則に縛られることなく活発に行動してほしいと思っています。ただほったらかしにしている訳ではなく、トラブルが発生したり、危険な目にあわないよう見守っているのです。
生徒指導としてではなく個人的に、これから夏にかけてパブリックな場所を通る際は、人に見られているということだけではなく、身の安全を守るためにも、露出度の高い服は出来る限り着用しないよう注意します。
結局この学校の最初のところ「あなた方は聖書をもっています。だから自分で自分を治めなさい。」という初代院長・矢嶋楫子の言葉に戻るのかな、と思っています。お母様方はどうお考えですか?
○
アンケートの結果から、お母様方が「服装の自由」を受容しながら毅然とした態度を失わず子どもと接している様子が浮かびました。又竹内先生のお話を通して、自由であり続けるための学校としての心配りを感じることができました。お忙しい中インタビユーを快くお引き受け下さった竹内先生、貴重な資料をお貸し下さった図書の梶原先生、又アンケートにお答え下さったお母様方、ご協力ありがとうございました。
(報告者雑感)
学校の紹介が大半で、入試問題の紹介は少々という点は例年と変わらず。昨年は、国語科と体育科の先生が壇上でお話しされたようだが、本年は数学科と保健・養護教諭のご登場となった。現場からの様子ということで、お二方の穏やかながら凛とした風情の漂う話しぶりからは、スマートなリーダーについて行こうとする授業内の生徒と、反面、心的に悩みを抱えてしまう生徒、という現場の両面が見い出される。特に甲藤保健・養護教諭の話された内容で、思春期成長期の身体的トラブルだけではなく、メンタリティーの回復に重点を置くのが保健室の役目である(ある意味、現在では常識になっているのかもしれない)という、生徒の精神的な「弱さ」を肯定的にとらえている面が興味深かった。「オアシスでなく、ステーションを目指す」ということばにも、その現状が垣間見えるようで、さらりとした内容ながらもその重さが伝わってくる。他校の学校説明会ではまず見受けられない保健教諭の登場は、高度な教科教育の後ろに、差し出がましい形ではない大人の寄り添いかたがあることを感じさせるものだった。
ところで、「自主性」は、実に耳障りのいいことばで、学校説明会に出向くと、このことばを聞かないことのほうが珍しいほどだ。他校では、時にこのことばに甘言的な危うさを感じる場面も多い。この「自由さ」をはき違えないだけの理解力や判断力を子供が持つのは、その年齢的成長を待つだけではなされないはずである。束縛はしないが、常に働きかける保護者と教師の取り組みがなければ、実現はしない。問題は、その取り組みの仕方が伝わるかどうかであろう。
今回の説明会で、学校側が本気で「自主性」の教育に踏み込んでいるなと感じたのは、田中院長、村瀬教務主事の「うまくいっていないケースもある」といった内容からである。田中院長の携帯電話の挿話にしても、「口ではりっぱなことを言うが、実際には教室で受信音を鳴らしてしまう生徒がまだいる」などの実情を、年3回の説明会で忌憚なく話されるのは、学校のイメージを考えると勇気のいることだと思うし、それだけに信念がないと出来ないことだとも思う。生徒の自主性に任せるというのは、ルールを設けた場合の倍以上の手間と労力が親と教師にかかる。確かに、塾の模試ではかれば「成績上位者」が入学してくるぶん、学力の側面だけに注目すれば生徒の学力的成長を待つ「重さ」は他校の負担には及ばないかもしれない。だが、本来の人格教育という側面ならば、相手が13~18歳の子供という点は変わらない。取り組みとしての重さは同じはずだ。今回の説明会でも、そのあたりの学校側の責任感が伝わってきたのは有意義だったと思う。ただ、2時間30分を講堂の小さな椅子に座っているのには、些か参ったが。(報告 A.Og)
http://www.joshigakuin.ed.jp/
横浜共立 学校説明会報告(03年11月8日)
司会
時間通りにスタートするのが横浜共立の習わし。
今年の説明会は午前、午後とも会場が一杯に。
挨拶 校長石井先生
1)今日、お集まりいただいた感謝として丁寧に学校のことをお話ししたい。
1871年に米国のプロテスタントの教会から派遣された3人の婦人宣教師によって創立。
2つの目的・・1 混血児教育・・当時の横浜の課題になっていた。
2 女子の教育・・文明開化の恩恵にあずかっていた多くは男性だった。
「西国立志伝」を書いた中村正直が学校を見聞して、当時の新聞に、アメリカミッションホーム(当時の呼び名)では国籍や親の階層等による分け隔てのない教育が行われ、子どもが大切に育てられているとの紹介記事を書く。
その精神を引き継いで、横浜共立は安心して生活できる学校の一つの現れとして、後援会が奨学資金制度を用意しており、中1からその制度を利用することが可能。
教育の根幹に一人一人の生徒を大事にしていこうという姿勢がなければ横浜共立の存在価値はない。
プロテスタントの教会による学校が山手にいくつかある。これらの学校同士は仲がよいがそれぞれの学校の個性がある。その個性とどう合うかが大切。
成績だけで学校を選ぶと子供たちに対して間違いを犯すことになる。
山手の学校に通う生徒達がお互いに挨拶の声を掛け合える間柄になれたらと思う。どこの学校に通っているかを子供たちが比較させられるような関係を私たちから変えていかなければならない。
2)キリスト教の学校
神を畏れ敬うということは人を尊重することにつながる。自分を中心としていたら相手を尊重できない。
礼拝が毎朝行われている。
聖書の時間が6年間にわたり1週間に1回ある。聖書をとおしてキリスト教について正しい知識を持つとともに、人間にとって大切なものは何か、人間のき方はどうあったらよいかを生徒と一緒に考える。
創立以来、教会との深い結びつきを持ってきた。教会が学園の精神の生命線であると言ってもよい。5日制を保っているのもそのため。日曜日に教会に行くことを強制はしないけれども、学園は教会の上に成り立っている。
キリスト教を理解することによって足ることを知ることができる。
子供たちがこれから進んでいく社会では順調でないことの方が多い。どんな境遇にあっても足ることを知るというのは、どれだけ子供たちを自由にし、謙遜にし、強くするでしょうか。
3)女子の教育を行う学校
創立当時は女子が重んじられることの必要性があった。それにより社会が健全になると考える。
現在は自分やその子どものために。
女の子だから、女のくせにという言い方をしてはいけない。女だから、女のくせにという言葉は子供たちの健全な教育を阻害する。女子だからという理由でしてはいけないことは何もない。
これまで女子だからという理由で先輩達がしてこなかった分野に積極的に出ていって欲しい。そういう思いを持って学習でも課外活動でも接していきたい。
青山学院の相模原キャンパスの開学式で、ひな壇に並んでいたのが全て男性だった。
OECDは母親が働きやすい環境を作れと日本に勧告している。結婚して子育てをした後に職場に復帰するのがきわめて難しい環境になっている。将来の労働力不足が言われているがこの環境を改善しないと日本の将来はない。
4)勉強を大切にしている学校
勉強を通して物事を正しく知る。世界、歴史、人間と出会い考える手だてとする。
明治27年の学則に、「教育の目的は和漢英の諸学を新しきに走らず、古きになずまずして偏重なく修めしめる」とある。
6年間を3段階に分けている。
基礎をしっかり学ばせて、その基礎がどう役立つのかを体験させ、将来の目的にかなった備えをさせる。
各教科が固有に持つ言葉と世界を自分のものにしてほしい。語学だけが言葉ではない。科学にも、社会にも、芸術にも言葉がある。その言葉を自分のものにしなければ、その言葉の持つ世界の素晴らしさを発見できない。
勉強は自分が素晴らしい世界を発見するためのもの。
知識から教養、教養から思想、思想から信仰へ。
5)横浜共立の生活
自主的な生活と共同の生活をめざす。
違った人たちが一緒に生活するためにお互いを大切にする。それはキリスト教でいえば個人の尊重と隣人愛の間に生まれる態度であり、基本的人権の尊重につながる。
授業で基本的人権の尊重を教わるが、それは遠いところにあるものではなく、私たちの目の前の生活にあるものだと知る。
挨拶をしよう。
時間を守ろう。
ものを大切にしよう。
躾が厳しいように思われるが、卒業して社会の中で生きていく上で、基本的な約束に忠実であろうということの現れ。
4代目校長(ルーミス)は、卒業生に「あなたがた若い世代の人たちはお母様やお祖母様たちが知り得なかった大きな自由を手にしていることを覚えていてください。考える自由、賢い選択をする自由、賢く行動する自由をよくわきまえなさい。それがあなた方の将来を切りひらく力となるでしょう」と言っている。
6)課外活動
高校2年生が書の甲子園に出して賞をもらった作品の言葉「若人よ今、一球に一打にかけて青春の賛歌をつづれ」に生徒の普段の生活が表現されている。
進路進学指導
高校生になると進路進学に関するさまざまな仕掛けが用意されている。
例えば高2では学問を体験する行事として大学の先生の講義を直接聞く機会が設けられ手いる。そうしたことを通じて自分が何をすべきかを自分で考える。それは生涯教育にもつながる。生涯教育の中での大学選びをして欲しい。人生に紆余曲折があっても筋が通っていればよい。
11月13日にノーベル賞受賞者の白川先生に来ていただいて講演をしてもらう。
学校として生徒のためにいろいろなことを考えてあげたい。
子供たちの将来が希望に満ちたものであるために、横浜共立のキリスト教教育の意味を理解していただき、横浜共立の個性を受け止めていただき、お子さんが横浜共立に合いそうだと思われたらお預けください。
学校生活等について 教務主任塚本先生
1)学校生活を教務的な側面から
中高6年一貫教育。高校募集がない。
2期制。
成績評価は以前から10段階の絶対評価。(一部の科目は5段階)
週5日制。土曜日は部活や課外授業、行事に。
週33時間授業。火、水、木は7時間授業。中学の総合学習の2時間は時間割の枠外で設定。
50分授業。(11月~1月は45分授業)
冬時間では14:30授業終了(7時限の日は15:20)。
8:20登校。17:20下校(夏期17:50、冬期16:50)。
石川町駅を利用する生徒が80%。通学路の途中にも警備の人が立つ。
習熟度別授業は高校の一部の教科(高1の数学、高2高3の英語の選択)で実施。
高2からコース分け。大幅な科目選択制。
日常的に質問受けや小テスト、ノートチェックを細かく実施。
必要があれば中1から高1には指名補習を夏休みの8日間を使って3科目が実施。各教科10名程度が指名されている。
高2、高3は受験補習を希望者対象に実施。有料。
専任教員の持ち時間比率が80数%。
自習の少ない学校。急な欠勤でも時間割を変えたりしてできるだけ授業を行う。
自習があれば自分が授業をしたいという先生が多い。
英語は創立以来の歴史と実績がある。
英会話は中1から高3までクラスを2分割。アメリカ人講師が4名。
教科書はこれまでプログレスを使用していたが04年から中高一貫英語教育研究会が編集したプレジャーに変更する。
部活動も熱心で高2までで全体の98%が参加。
年4回の定期試験の前1週間は活動を休む。
大学入試では現役での合格、進学率が高い。03年度の大学合格者のうち89%は現役が占める。03年の現役での進学率は87%。年によっては90%を超える。
2)03年入試結果
A試験 B試験
定員 150 30
応募者数 405(199) 546
受験者数 384 328
合格者数 162( 99) 77
追加合格 6 39
入学者数 152 28 ( )はA・B重複受験生
合格者平均
国語 63.3 82.2
算数 65.9 69.5
社会 69.6
理科 56.0
合格者最高 73% 91%
合格者最低 59% 71%
3)04年入試関して
A試験が2月2日、B試験が2月4日。
筆記試験は総合点で判定。
願書受付初日は6:00に開門。整理券を配布。あまり早くから並ばれないようにお願いします。
願書は黒のボールペンで楷書にて記入。入学後の名簿やゴム印作成の元になる。
緊急連絡先は自宅以外で連絡がつくところを。携帯電話でも可。
備考欄には例えば引っ越しの予定とか名前の難しい字を大きく書いていただくとか、特に学校側に承知しておいて欲しいことを記入。空欄でも可。
通知表のコピーはB4サイズの両面に収まるように。
入試当日に関して
7:30 開門
8:30 受験の注意の説明
8:40 点呼・・・これに遅れると受験できない
8:50 開始
昼食は試験会場でとる。
面接は03年の入試ではA試験で16:05、B試験で13:30が最終時間だった。
面接は8~9部屋を使用。教員3人:受験生5人のグループ面接。1組15分。
5人のグループは欠席者を除いて番号順に。
A試験で面接をした人はB試験の面接はなし。昼食を取らずに帰れる。
面接に際して服装の気づかいは不要。
その他に関しては出願時に渡す受験上の注意のプリントを参照。
入試問題に関して
円周率を使うときは3.14で。
ここ数年間と同じ出題レベルを考えている。
追加合格に関して
A試験、B試験それぞれの欠員分をTELで連絡。
A試験の繰上は2月4日15:00以降。
B試験の繰上は2月5日15:00以降。
同点者には一律に連絡。
2月14日(土)に招集日を設けているので2月13日までには繰上は終了。
入学を辞退された場合、手続時納入金のうち施設費を返還。
A・B両方に出願されていて、Aで合格された場合、Bの受験料は返金。
4)説明会終了後、130周年ビデオの放映と校内の自由見学あり。
(報告 A.A)
http://www.kjg.ed.jp/top.htm
穎明館 学校説明会報告(03年11月20日)
1) スライド 穎明館の四季
2) 教育方針・教育の現状 久保田校長
〈2003年の穎明館教育〉
穎明館はまだ若い学校。穎明館の教育を作り上げている段階。
教育には不易の部分と流行の部分がある。教育界の動き、入学してくる生徒の違いに合わせて変化していくことも必要。
学校案内に2003年の穎明館教育と書いてあるのはそういう意味。
穎明館では入学式のすぐ後に全校保護者会を実施し、穎明館の教育の実態を報告し、学校としての説明責任を明らかにしている。
〈知的生活の場〉
穎明館は進学校として創立される。
21世紀記念館ができハード面は完成。
この施設の中でノーブレスオブリージェの精神を培って欲しい。
そのために真善美の調和を図る。
真・・知識
善・・道徳
美・・芸術的な感性
知識に優れ道徳的であるだけでなく、芸術的な感性がこれからのリーダーには重要な要素。芸術的な感性があれば国を超えて感動を共有することができる。
EMKのEは経験。さまざまな体験が出来るように理科実験室も充実させる。
これからはさらにソフトの充実に力を入れる。
学力と共に人格の形成も両立させる。その結果として大学進学実績もよくなっていく。
学校は楽しくなければいけないが、それは縁日の楽しさとは違う。
知的生活の場として文化的、知的な雰囲気が漂う楽しさ。
今年から朝7:00から開校。図書館、教室で自習や講習が出来るようにしている。
下校時間も、もっと残っていたいという生徒の希望に応え、18:30から19:30に延ばす。
〈キャリアエデュケーション〉
人間は素晴らしい知識を持っているが自分に対する知識を持っていない。→自分を見つめ将来の自分を考えるために6年間を通したキャリアエデュケーションを行う。
中1から高3までを6段階に分け、生徒個々の成長に合わせた指導ができるように進学カードを作成している。
大学も自分の将来の希望に合わせて選択する時代。中学から自分の将来を考え、高校に行ったら自分の方向が決まるように。
〈教養重視〉
高校で文系、理系分けはあるが、厳密な分け方はしない。選択により時間数や内容は変わるが、高2までは全員社会、理科、数学を履修する。多くの教科を学ぶことによって教養を身につける。
数学は論理的思考を養う上で必要。第二外国語も国際人の育成などと上段に構えるのではなく1個の人間の教養として学んで欲しいと思い設定。第二外国語を担当するネイティブもそうした穎明館の方針をわかってもらえる人を選ぶ。誰でもいいというわけではない。
〈学習指導〉
シラバスもこれまでは学年ごとのものだったが、6年間を見据えた教科別のシラバスに変える。
評価は穎明館のレベルを設定した上での絶対評価。全員を5に引き上げる努力をしなければならない。
通知表の所見欄も本当の意味の所見にならないので廃止。家庭との連絡を密にするために連絡ノートを作る。
夏休みは40日あるが7月中は補習、補講。
小学校では上位の子が入ってくるが徐々に差がつく。中1では以後困らないように7月中に指名補習。
高3は大学受験用の補講。
8月1日からはクラブ合宿。先輩が手伝いにきてその時大学の様子を話してくれる。
〈その他〉
シャープな頭と思いやりの心の両立した生徒を育てたい。
心の相談室を設け、心療内科の医師が来ている。生徒の悩みの受け皿に。
生徒の成長には父親の協力が必要。父親の会を年1回開いている。500名近い父親が参加。昨年の会で朝ご飯を食べないで登校している子がいるという話が出る。調べたら300名近くが朝食抜きだった。食堂で朝食が出せるようにする。30~40名が利用している。
昼は原則として全員スクールランチ(給食)。
中1、中2は弁当持参も可。
中3以上はアレルギー等の特別な事情のある場合を除いて。
アメリカではゼロトレランスという言葉が産業界から教育界に広がっているが、穎明館はフルトレランスで行く。生徒を信頼して見守っていく。
学校、生徒、家庭が思いやりを持って接して行くことが大切。
3)教科指導と進学指導・・各教科から
数学
入試問題は03年と同じ形式、レベルでの出題の予定。
計算問題は減っている。
試験時間が60分から50分に。その分、問題数を減らす。
昨年から1問は記述式の解答に。
入試対策としては、過去問題にあたってもらうのが一番よい。
数学の授業
中1から高1まで週6時間授業。中3から高校課程に入る。
高2で理系志望者は週7時間、文系志望者は週5時間。
学習指導要領の改訂で中学の内容が大幅に高校に先送りされる。高校からの入学生は公立中でやってきていないのでやりづらくなっている。
中3までは授業はHR単位で。高1では習熟度別授業(2段階)。
国語
入試問題の傾向、レベルは例年と変わらず。
試験時間が60分から50分に。文章の長さを少し短くする。
長文2題と漢字、文法(言葉のはたらき)。
記述問題は文章中に必ずヒントがある。
記述の解答にはその子の持っているものが現れる。
国語の授業
最初は慣れることから。
中3で高1までの内容が終わる。
今の教科書の内容が軽くなっている。文学的文章より説明的文章の方が多く、生徒は読めばすぐわかる内容のものが多い。
有名作品の朗読を授業前に行っている。
小論文に対応できるように、評論を読んで考える力をつけるようにしている。
中1の終わりから古典文法を学ぶ。
1月には百人一首大会を行う。
日本語で考えるのと英語で考えるのとは違う。
日本語は日本の文化を理解する上で必要。
進学指導
中1は学校生活に慣れると共に学習週間をつけること。
進度に合わせた学習ができるようになればよいが、徐々に力の差が出てくる。
自己理解・・自分の興味、適性を知る。
中3で卒業論文を作成。就職ガイダンスを行う。
高2から文系、理系分け。
高3ではコース制。国公立理系、私立理系、国公立文系、私立文系の4コースに。
4)03年大学入試結果(説明会資料より)
東大 一橋 東工大 東外大 東北 筑波 北大 国公立計
総数 2 4 4 1 3 4 2 63
現役 2 3 4 1 0 4 1 41
早大 慶大 上智 明治 青山 立教 中央 法政 理科大
総数 42 30 21 28 20 12 43 12 38
現役 30 26 16 20 10 6 26 10 27
=卒業生190名に対する東大、早慶上への現役合格者数の割合(A率)は38.9%。MARCHへの割合(B率)は37.9%。昨年のA率は35.1%、B率は40.2%。=
一橋、早稲田、上智は過去最高の合格者数。
5)03年入試結果
1回(2/2) 2回(2/4)
募集人数 男女100 男女 60
男子 女子 男子 女子
応募者数 323 95 306 101
受験者数 302 87 206 76
合格者数 162 29 87 30
受験生平均
国語(120) 50.9 55.0
算数(120) 65.8 52.2
社会( 80) 42.9 38.2
理科( 80) 44.8 38.9
合格最低点 212 203
教科別合格者最低点(1回)
国語(120) 31・・・算数は92点取っている。
算数(120) 45
社会( 80) 28・・・算数は94点取っている。
理科( 80) 28
合否は4科の総合点で判定。足切り、男女の区別なし。
募集定員は160名だが1回、2回で300名近い合格者を出す(繰り上げ合格も含め)。
教科別合格最低点でもわかるように、1科目が悪くても他の科目で補って合格している。
重複受験生に加点等の配慮はないが、1回不合格者のうち84%が2回を挑戦している。
1回と2回で受験生平均は合計点で20点近く下がっているが、重複受験生の平均点は2回の方が11.6点あがっている。算数では13.4点上がっている。
1回不合格で2回を重複受験した受験生の67%が2回で合格している。
04年から重複受験する場合は2回目の受験料を不要にする。
入学者の男女比は例年男子3:女子1。学校全体では10:3の割合。
女子は応募者が男子より少ない上、算数で男子に差をつけられている。平均で15点差がある。
入学後の学校生活は心配ない。女子の方がまじめに取り組んでいる。それが進学結果にも現れている。今春東大、早慶上に28名合格。女子の卒業生49名の57%にあたる。
6)04年入試に関して
1回 2月2日 男女約100名 4科
2回 2月4日 男女 約60名 4科
試験時間を変更。国語・算数各60分を各50分に。社会・理科各40分を各30分に。
配点を変更。国語・算数各120点を130点に。社会・理科各80点を70点に。
試験時間を各教科10分ずつ短縮したため終了時間が早くなり、昼食は不要に。
入試問題は受験生平均で50%、合格者平均で60%を目安に作問する。
試験時間が短くなるので問題量が減る。小問の比重が高くなる。
願書の帰国子女欄は帰国生枠での入試を希望する人が記入。
帰国生の条件として海外在住2年以上、帰国1年以内だが、帰国時期に関しては状況によるので相談を。
帰国生枠での入試希望者は国、算、英での受験も可能。英語は50分でうち10分はヒヤリング。英語の内容は英検3級から準2級程度。面接あり。
7)説明会を追加
12月16日(火)10:30~12:30
説明会終了後に個別相談の会あり。
(報告 A.A)
http://www.emk.ac.jp/
渋谷幕張 卒業生が大腸ポリープの原因発見に貢献
(朝日新聞 11月17日)
大腸に多数のポリープ(突起)ができてがんにつながる病気が、腸の細胞の染色体に関係する遺伝子の異常で起きることがわかった。京都大医学研究科の武藤誠教授や大学院生の青木耕史さんらのグループが突き止め、17日付の米科学誌ネイチャー・ジェネティクス電子版で発表する。がんの予防法開発などに役立つ可能性があるという。
大腸に数百から数千のポリープができ、がん化する病気「家族性大腸ポリポーシス(FAP)は1万7千人に1人発症するとされる。武藤教授らは腸の細胞ができる時に重要な役割を果たす遺伝子「Cdx2」と、がん抑制遺伝子「Apc」に注目した。二つの遺伝子の働きを抑制したネズミの大腸を調べると、生後10週間で80個以上のポリープが発生し、FAPと同じ症状になっていた。ポリープの細胞では染色体の異常が通常より10倍多かった。=文章中の大学院生が渋谷幕張の卒業生とのこと=
http://village.infoweb.ne.jp/%7Efvgf5660/
桐蔭学園 ラグビー部が3年ぶり4回目の花園へ
全国高校ラグビー神奈川県予選の決勝で桐蔭学園が26―10で東海大相模を破る。
大個別相談会
日時 12月13日(土) 10:00~12:30
内容 ブースでの個別相談会
入試説明会
クラブ活動発表会
校舎内施設見学、クラブ活動見学
http://www.cc.toin.ac.jp/GAKUEN/
公開模試情報
三模試志望者数前年対比 (11月度)
三模試の学校別志望者数前年対比をアクセス教育情報センターの会員のページに掲載しております。
下記をクリックしてご覧ください。
教育情報
県千葉を中高一貫校に 県立高校再編案
(毎日新聞 11月20日)
県教委は19日、06年度から08年度までを実施年度とする県立高校再編計画の「第2期実施プログラム案」を発表した。千葉に新たに中学校を併設して中高一貫校とするほか、銚子商・銚子水産・柏北・柏西など12校を6校に統合するなど、計19校の再編案を示した。「第2期」が完了すると、現在142校ある全日制高校は129校となる。県民からの意見募集などを経て最終決定する。
県立高校の再編については中学卒業人口が減少することや普通科志向の高まりを受けて、県教委が一昨年9月に、昨年度を初年度とする10年間の「県立高等学校再編計画」を策定した。今回のプログラム案は、昨年7月に発表した「第1期実施プログラム案」(実施年度は06年度まで)に続いて2回目。
千葉に新たに併設される中学校は40人学級で2クラスを予定している。学区は問わず県内全域から応募することが可能で、中学入学時は学力試験は行わず、作文や面接で選抜する。内部進学者は高校進学時にも学力試験は行わない。高校は学力試験による入学者も受け付ける。県教委は「千葉高のこれまでの進学校としての伝統を考慮し、より高い学力をつけたいというニーズに応えられるようにしたい」
と話している。これに伴い定時制課程は07年度以降募集を停止し、在校生は08年度から定時制3部制の生浜に転入する。
統合される12校のうち、銚子商と銚子水産については、地元の銚子水産OBなどから「銚子市には水産教育の柱が必要」と知事あての陳情書が出るなど、反発する動きも出ている。
生徒が将来に進路に合わせて科目を選択・履修できる単位制は、新たに市原八幡、千葉東、船橋西に設置される。
公立高教員公募制 千葉県教委が導入
(毎日新聞 11月25日)
千葉県教委は、現職の高校教員が県の指定する重点校の中から、勤務を希望する高校を選んで応募する「公立高等学校教員公募制」を来年度から導入する、と発表した。
公立高は私立高に比べ、学校の特色に合わせた教員の配置が難しく、生徒や保護者のニーズに応えられないケースが多いので、導入を決めた。同様の制度は、東京都が01年度末から導入しており、埼玉県も来年度から実施する。
公募制の対象となる高校は、浦安▽姉崎▽千葉東▽船橋▽佐原▽木更津▽長生――の計7校。浦安と姉崎は、県が「自己啓発指導重点校」に指定。他校に比べて中退者が多いため、生活指導面で能力のある教員を必要としている。一方、残り5校は県が「進学指導重点校」と定め、進路指導で力を発揮できる教員を求めている。
応募の条件は、現在の高校に3年以上勤務していること。希望者は特技やこれまでの経歴などを必要書類に記入し、所属長に提出する。所属長が意見を書き加え、県教委に提出し、年度末には異動が決定する。
県教委は「実力が発揮できる場が選べるという点で、生徒にも教員にもメリットのある制度」と話している。
都立進学指導重点校 指定延長と新規指定について
(11月27日 東京都教育庁)
東京都教育委員会は、特色ある学校づくりの一環として進学対策を充実させるため、平成13年9月に「進学指導重点校」として4校を指定し、この4校に続いて平成14年9月には「進学指導重点準備校」を3校指定しました。今回、平成16年3月31日に指定期間満了を迎える「進学指導重点校」については指定期間を延長するとともに、「進学指導重点準備校」を「進学指導重点校」として新たに指定しましたので、お知らせします。
1 進学指導重点校及び指定期間
(1)指定期間を延長する学校
平成13年9月26日~平成19年3月31日
日比谷高校
戸山高校
西高校
八王子東高校
(2)新たに指定する学校
平成15年11月27日~平成19年3月31日
青山高校(旧準備校)
立川高校(旧準備校)
国立高校(旧準備校)
2 進学指導重点校の指定期間を延長する理由
進学指導にかかわる各校の取組みは充実されてきているが、指定期間を延長することにより、さらなる実績向上が期待できる。
3 進学指導重点準備校を進学指導重点校に指定する理由
進学指導への取組状況、学力検査問題の自校作成、昨年度の進学実績を判断すると、進学指導重点校に指定することにより、さらに進学指導の充実・改善が期待できる。
4 主な支援策
(1)進学を重視した教育課程の編成
(2)公募制の導入による指導力のある教員の配置
(3)習熟度別授業の実施に必要な教員等の措置
(4)土・日曜日の補習を充実させるための必要な措置
(5)その他、進学指導の充実に必要な措置
5 進学指導重点準備校の指定について
進学指導重点準備校については平成16年度は新たに指定しないが、進学指導重点校以外の高校の自律的な進学指導への取組み及び実績等を勘案して、今後指定を検討していく。
都立高合同講習 「つどいin冬」の実施について
(11月27日 東京都教育庁)
東京都教育委員会では、「つどい in 夏」に引き続いて、大学進学等を希望する都立高等学校の2年次生の生徒に対して合同講習「つどい in 冬」を下記のとおり実施します。
この講習は、都立高等学校の「授業改革の推進」事業の一つで、生徒が互いに学び合い、自ら課題を見付けて自ら学ぼうとする態度や問題を解決する能力などの「確かな学力」を身に付け、自己の進路実現を目指す生徒を育成するものです。
また、この合同講習は、都立高校の“選りすぐられた教員”が講座を担当し、都立高等学校の教員に公開することによって、自ら教科指導の改善を図り、教科指導の実践的な指導力の向上を目指すものです。
記
1 実施期間
平成16年1月5日(月)から1月7日(水)までの3日間
時間は、午前9時から午後4時10分まで
2 会場
東京都教職員研修センター分館 東京都総合技術教育センター
3 ねらい
ア 教員の教科指導力の実践的な向上を図る。
イ 都立高校教員に公開し、教員の自己啓発を図る。
ウ 生徒の授業に対する意識改革、自己の進路実現を図る。
4 実施方法
(1)担当講師 都立高校の“選りすぐられた教員”が講座を担当
(2)対象 大学進学等を希望する都立高校の2年次生相当の生徒
(3)実施教科 国語、地理歴史、公民、英語、数学、理科、商業、工業
(4)応募方法 講座単位で学校に申し込む
5 内容
(1)大学入試センター試験を基準とした内容
(2)商業、工業については、資格取得につながる学習内容
(3)基礎的基本的事項の理解に立った発展的・問題解決的な内容
6 規模
(1)受講者数 延べ2,520名
(2)講師 延べ168名
(3)講座 28講座×3日間
私立高校の学費滞納 1校当たり平均13人と過去最高に、神奈川県
(毎日新聞 11月28日)
県内の私立高校の学費を3カ月以上滞納している生徒が、過去最悪の1校あたり平均13人に達したことが26日、神奈川私学教職員組合連合(長谷川正利委員長)の調査で分かった。長引く不況と親のリストラが、私学で学ぶ生徒に深刻な影響を与えている現状が浮き彫りになった。
◇不況深刻…修学旅行不参加も
調査は98年から毎年行っているもので、今年が6回目。今回は10月に実施し、県内私立学校(全日制)76校のうち、高校35校(生徒数3万5182人)と、併設する中学校22校(同7898人)から回答を得た。
調査結果によると、高校では9月末現在、3カ月以上の学費滞納者は計450人(昨年310人)で1校平均13人(同9人)。6回の調査で初めて2けたになった。
経済的な理由での修学旅行不参加者も計34人(昨年21人)と過去最悪。最も多い学校では、不参加者が20人に上ったという。経済的な理由での退学者は計20人だった。
中学では3カ月以上の学費滞納者数は計51人で昨年と同じだったが、経済的な理由での退学者が4人出た。退学者が出たのは今回が初めてで、中学でも学費負担の深刻さを反映する結果となった。
神奈川私教連は「自営業者の倒産や失業が顕著で、保護者が失業すれば、直ちに退学せざるをえないという切迫した状況になっている」と分析。リストラされた父親が自殺したケースもあったという。
また、滞納者が年々増加している背景として、県の私学助成金が全国で最低レベルであることを指摘。県によると、02年度の神奈川の私立高校生1人あたりの私学助成金は26万1100円と全国最下位。初年度納入金の公私間格差は7倍だった。私教連は来月、学費補助制度の拡充や私学助成の増額などを求める請願書を県議会に提出するという。
小中一貫校を設置 三鷹市
(NHKニュース 12月4日)
東京・三鷹市は、平成17年度から試験的に1つの学区で9年間を3段階に分ける独自の小中一貫教育を導入します。最初の2年間は規律ある生活や学習習慣、次の3年間は基礎学力充実、最後の4年間は個性や能力育成としています。
その他
自衛隊イラク派遣
(毎日新聞 11月17日ワイド特集より)
「女の気持ち」は本紙生活家庭欄の投稿コラムだが、最近、自衛隊員の妻から匿名で手紙が届いた。住所や電話番号の記載がないのでコラムで採用できないが、ここで紹介する。
「お父さんイラクにいくかもしれんよ。お母さん、気持ちをしっかりもっていてね」と、夕御飯のとき夫が言いました。私は前々からの不安が現実になった様に思って言葉が出ませんでした。結婚して十数年、家庭は誠実でしっかり者の夫があればこそ、頼りにしている大黒柱です。その日は眠れませんでした。自衛官という職業、でも何故、うちの人がイラクに行かなければならないのでしょう。夫の両親も行かせたくないに違いない。私が一生後悔することが起きるかもしれない。子供は泣くでしょう。
次の朝、私は言いました。「お父さん、イラクに行かないで。行くなら辞めていいよ、夫婦で働けばなんとかなる、お母さんは苦労こわくないよ」。幸せだった結婚生活、今度は私がお父さんを守ります。命を誰かのために無駄にして欲しくない。たとえ私や子供のためでもいけません。
小泉首相とブッシュ大統領がテレビに映っていました。お酒を飲んだ後の酔ったような顔で、肩を抱き合っていました。「この人たちに夫の命が--」と思うと、その軽い雰囲気に愕然としました。
いつも私が悩んでいるとき、お父さんは「今、出来ることをしてみたらいいよ」とアドバイスしてくれます。今出来ることってわからない、ただ祈るだけしかできない。
こういう心配、こういう視線を首相は忘れないでほしい。イラクはますます泥沼化し、すでにゲリラ戦である。どこが安全、どこが危険という議論は無意味だ。この際、自衛隊の派遣は延期した方がいいと思う。それが常識的で賢明な判断だ。日本には憲法がある。自衛隊以外の貢献も考えた方がいい。
戦争は、相手に戦う意思が残っているのに勝利宣言したら負けだ。今後アメリカの劣勢が日に日に明白になっていくだろう。①フセイン独裁体制を倒す②民主的・親米的な政府をつくる③この過程で米国の軍需、石油産業が潤い、復興で他の米国企業も潤う--というシナリオだったと思うが、占領統治は大失敗。米国は②以下はあきらめ撤退するべきだ。撤退を忠告できるのは日本と英国。ベトナムの教訓を想起してほしい。
=治安の悪化を理由に来年5月の総理大臣のイラク訪問構想が宙に浮いたという記事が出ていた。為政者は国民に戦うことを求めても自分では戦いに赴かない。イラクへの自衛隊派遣は国益に添うものだと言われるが、国益とは誰の利益なのか。国を治めるものの利益か、国民の利益か。為政者にとっての利益と国民にとっての利益とが一致していないのではないか。国民は総理大臣が他国に行ってもてはやされ、芸術鑑賞を楽しむために税金を納め自分の命を預けるわけではない。=
<問題>
図のように,3種類のおもり●,■,▲をのせたてんびんがつりあっています。▲の重さを求めなさい。(03年西南学院)
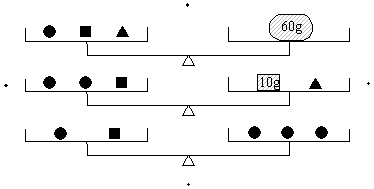
入試問題に挑戦第97回解答編
<問題>
かき3個,みかん4個,りんご5個を買うと代金の合計は940円ですが,かきとりんごの個数をとりちがえて買ったため,代金の合計は900円になりました。りんご1個の値段はみかん1個より50円高いです。かき,みかん,りんご,それぞれ1個の値段はいくらですか。
(03年同志社女子)
<解答>
かき3個、みかん4個、りんご5個 → 940円
かき5個、みかん4個、りんご3個 → 900円
ここからわかることは、りんご2個をかき2個に変えると代金が40円安くなるということ。
つまり、40÷2=20円がりんご1個とかき1個の値段の差。りんごがかきより20円高いことがわかります。
また、2通りの買い方を一緒にすると、
かき8個、みかん8個、りんご8個 → 1840円 となるので、各1個の合計は1840÷8=230円。
あとは分配算で、りんご1個の値段にそろえればよい。
(230+50+20)÷3=100円 … りんご
100-50=50円 … みかん
100-20=80円 … かき
以上から、かき80円、みかん50円、りんご100円です。