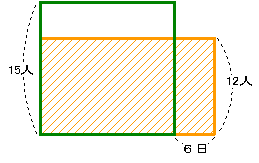NO.104
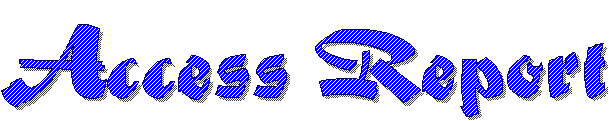
2003年 7月15日
アクセス教育情報センター
目次
|
学校情報 |
学校情報 | 入試情報 | 教育情報 | その他 |
| 海城中 | 聖セシリア | 合同招集日
公開模試情報
|
教員異動 | 保護者アンケート結果 |
学校情報
海城中 塾対象説明会(03年7月7日)
和田校長
05年入試から入試変更
中学 社会、理科の配点を各60点から各80点に。
国語・算数の配点、各教科の試験時間は同じ。
高校 英語にリスニングを導入。英語の試験時間を50分から60分に。
リスニングの配点は100点中20点。
新学習指導要領のもと、海城の指導内容に関して、プロジェクトチームを作って検討中。
受験生が海城のことを少しでも理解できるように、ホームページに校長からのメッセージを載せている。
茂木広報部長
1 海城の使命は「新しい紳士」を育成すること。
そのための四つの柱
① フェアな精神
② 思いやりの心
③ 民主主義を守る意志
④ 明確に意志を伝える能力
2 海城のアドミッションポリシー(海城はどういう生徒をもとめているか)
進学校を保護者の方はどこも同じように捉えている。そのため大学進学実績の数で学校を見るが、大学入試に向かうまでのプロセスが学校によって違う。
海城は大学に入りさえすればよいとは思っていない。
カリキュラムを見てもらえば海城の考え方が理解してもらえると思う。
高校1年までは全員が同じ授業を受ける。
高1では理科総合A・Bが2単位ずつある。理科総合を高3にまわして問題演習にあてている学校もあるのではないか。海城ではこの時間で、オリジナルの図説を使いながら、本来の意味での理科としての総合をやりたい。
中学での総合学習(各学年2時間ずつ)では、これまでの総合社会を踏襲していく。
そこでは社会科が中心となってチームティチングで授業を行う。
高1までは学問の本質的なものを身につけて欲しいと思っている。
高2ではこれまで文A、文B、理系の3コース制だったが、現在の高1が高2になるときから文系、理系の2コース制に。
文系は高2、高3で理科の物理、化学、生物、地学のうち2科目を選択する。
理系は高2、高3で物理、化学、生物が必修になっている。
文系、理系も高3の最後まで全ての教科の授業がある。12月の期末テストをクリアーしないと卒業できない。
専門的な知識を大学、大学院で身につけるために、高校で基礎、基本、教養を身につけた上で進学して欲しい。
高2からのコース分けは生徒が自分で決める。高1の11月に。
したがって、文系、理系のクラス数はあらかじめ決まっていない。
6月段階の予備的な調査では50%が理系希望、20%が文系希望、30%が未定だった。
高校からの入学生は理系志向(医学部志向)が強い。
大学も自分の行きたいところを受けなさいという方針。それが決まった後で個人別の進路指導を学校は行う。
今春391名が卒業。9割はどこかに合格しているが、進学は6割。
海城の授業は先取りはせず、学問の本質的なことを学ばせる。
社会Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(総合学習と名前は変わったが)を通じて自分で調べることや、中3では卒論をまとめたりする。そうしたことは時間のかかることだが大事なこと。
高1までは教科書的な進度は公立とさほど変わらない。その分+αの部分が入っている。教科によっては高校の教材を補助教材として使っている。
大学受験に関係ないことを切り捨てて、大学入試に特化したやり方を望む人(生徒・保護者)には合わない学校。
新課程で学習している中学生が現中1、中2。現高1の高校からの入学者は移行措置の学年の生徒だが、以前の入学者とあまり変わっていないという印象。
ただ、将来のためにプロジェクトを設けて新課程への対応をシミュレーションしている。
3 入試に関して
① 05年からの中学の入試変更について
社会・理科の配点変更 各60点から各80点に。
海城も4科目入試になって10年以上。また、4科目入試の学校が増え4科受験生が普通になってきた。
現状では国語・算数のウエートが高い。(国120、算120、社60、理60)
授業時間の割合も国語・数学:社会・理科がおおむね6:4
高3まで全教科必修になっている。
等の理由から社会・理科の比重を上げて、海城に合った受験生が入りやすいように変える。
② 05年からの高校の入試変更について
リスニングは学内のテストでは既に実施している。
05年度入試の広報活動が始まってからリスニングの模擬問題を配付する予定。
③ 04年入試
願書は12月1日以降配布。
帰国生の入試は一般入試と一緒に行う。面接は本人のみ。事前に作文を書いてもらい、それを材料にしながら面接を行う。
SARSの認定地域からの帰国生は帰国してから10日以上経過していることを条件とする予定。その受験生に責任があるわけではないが、他の一緒に受験する生徒への配慮から。
質疑応答
1 大学入試結果で医学部だけの合格者数をまとめているのは。
外部からの要望が多いため。
2 留年する人数は。
年にもよるが多いときで5名くらい。成績不振者には講習等で対応して進級できるようにせているが、学習に対する意欲を失ってしまった生徒が問題。年2回個人面談があり、そこで、なぜ学習への活力を失ってしまっているのかをつかむようにしている。
3 05年からのリスニングのレベルは。(高校入試)
海城の中学生には各学年でNHKの基礎英語を聴くよう課題が出ている。それからするとNHKの基礎英語3程度になるのではないか。
4 入試で調査書の占める割合(高校入試)
調査書に関しては内規で段階があり、一番下の段階になった場合、その受験生が筆記試験で合格点に達していた場合、審議対象となる。審議の結果、合格した例もあれば不合格になった例もある。
5 入試の出題と新学習指導要領(高校入試)
海城中の授業は新課程にとらわれず行っており、新学習指導要領にはとらわれない。
6 入試での足切り点はどの程度か。
点数は非公表。ただ入学した生徒が同じ授業を受けるにあたり、あまりかけ離れた教科があると大変なので。試験後、平均点等を参考に教科会議を開いて決める。全体平均点のかなり下の点数になっている。偏差値換算した場合40よりもっと下。(全体平均点の半分くらいか・・報告者注)1科目でもそのような点数があれば、合計で合格点に達するのはかなり難しい。
7 03年中学入試の受験結果は。
1回 2回
応募者数 445 1123
受験者数 411 700
合格者数 148 247
合格最低点 185 211
(360) (360)
入学者数 257名
8 社会の記述に関して採点基準等は。
海城中の定期テストは3~5割が論述形式。理解の質を見たいため。
例えば、刀狩り関して誰が何年にというより、なぜ刀狩を行ったのかを聞く。
海城ではそういう学習を行う。
小学校の教科書の中に説明してあることが理解できていることが前提になる。
考えるために必要な小学校の教科書に載っていない知識やグラフは問題文の中に入れてある。
また、問題文の中にどういうふうに答えればよいかの条件を入れてある。例えば、~の表をもとにして答えなさいとか、~をふまえて答えなさいというように。その条件に従って書けていれば部分点をあげている。
採点は複数で行っており、評価が分かれたときは調整する。
教科書に載っている漢字は漢字指定をしている。それ以外はカナで書いてもよい。(例 大くま重信)
記述が誤字だらけの場合は減点されることもある。
字の上手い下手で加点、減点はないが、相手に読んでもらうのだから丁寧に書いて欲しい。
字数制限の字数は、子供として要求した項目に答えればこの程度の字数が必要だろうというところを目安にしている。要約が上手くできていれば字数が少なくても満点になることもある。ただ、字数が少ないときは項目を外していることが多い。
字数オーバーは条件違反として減点対象になる。
記述の内容として出版社が模範解答で出しているような答は求めていない。
04年入試要項
1回 2月1日 男子120名 4科
2回 2月3日 男子120名 4科
入学手続は1回が2月2日16:00まで。2回が2月4日16:00まで。
2月28日までに入学辞退をした場合は納付金(48万円)のうち施設費、教育充実費(18万円)を返金。
03年大学入試結果
東大 京都 一橋 東工大 東外大 東医歯 東北 千葉 国公立計
総数 51 4 19 17 5 2 8 6 169
現役 34 2 11 9 4 2 2 5 99
早大 慶大 上智 明治 青山 立教 中央 法政 理科大
総数 161 144 28 53 7 16 27 19 106
現役 84 86 13 23 4 10 20 4 33
=卒業生391名に対する東大、早慶上への現役合格者数の割合(A率)は55.5%。MARCHへの割合(B率)は15.6%。昨年のA率は66.1%、B率は7.3%。=
(雑感)
校長先生の話が入試要項の変更にしか触れなかったのは残念だった。入試に関する話を中心にするにしても海城における中学入試の意義をしっかり話して欲しかった。
社会の記述にしても会場からの質問があったから記述を行っている意味や記述に対する海城の考え方が伝わったようなもの。本当はそうした話がアドミッションポリシーのところでされていてもよかったのではないか。
(報告 A.A)
http://www.kaijo.ed.jp
サレジオ学院 04年入試要項
A 2月1日 男子 100名 4科
B 2月4日 男子 60名 4科
A試験の入学手続は2月3日16:00まで。B試験の入学手続は2月5日16:00まで。
行事日程
学校説明会
9月 6日(土) 14:00~
10月18日(土) 14:00~
11月15日(土) 14:00~
サレジオ祭
9月20日(土)、21日(日)
http://salesio.netty.ne.jp/
城北中 行事日程
クラブ公開 予約不要
9月27日(土) 13:30~
クラブ活動の見学、体験参加
入試説明会を講堂で同時開催
オープンキャンパス 事前予約制
10月25日(土) 13:30~
英語教室 20名
理科実験教室 物理・生物各24名
申込方法 必要事項をもれなく記入の上、往復ハガキにて。
9月8日(月)~10月2日(木)必着。申込み多数の場合は抽選。
記入事項 1 参加ご希望の教室名(理科の実験教室は物理と生物のどちらか1つを選択)
2 お子様のお名前、学年
3 保護者の方のご氏名
4 ご連絡先(住所・電話番号)
5 返信ハガキの宛名欄に郵便番号・ご住所・保護者氏名を記入
宛先 〒174-8711 東京都板橋区東新町2-28-1
城北学園 オープンキャンパス係
http://johoku.ac.jp/
筑波大駒場 学校説明会
1.実施日時:平成14年10月11日(土)、12日(日)
10:00~11:30
13:00~14:30
15:30~17:00
計6回,各回定員470名
2.会場:本校7号館3階
3.申し込み方法:
9月1日から9月25日(消印有効)までに、参加人数(1名または2名,最大2名)及び希望日を往復はがきに記入し、本校宛に郵送して下さい。
(いずれの回にご参加いただくかは、本校で決めさせていただきます。)
宛て先:〒154-0001 世田谷区池尻4-7-1
筑波大学附属駒場中学校 学校説明会係
往復はがき記入例
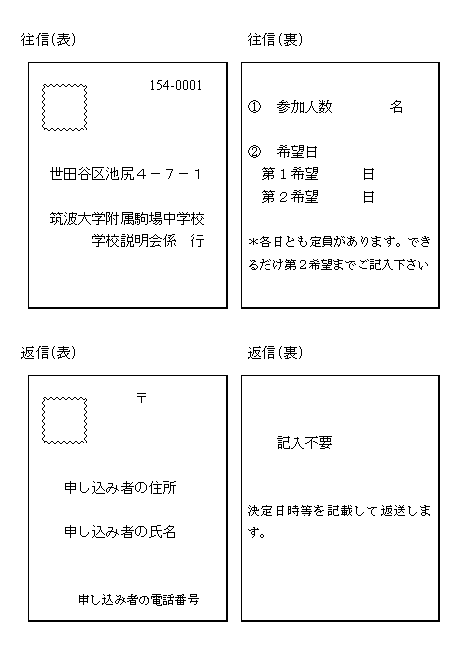
http://home.catv.ne.jp/dd/tukukoma/hp/index.htm
横浜中 04年入試要項
1次A 2月1日 男子40名 2科4科
1次B 2月1日午後 男子60名 2科4科
2次 2月3日午後 男子40名 2科4科
3次 2月7日 男子20名 2科4科
http://www.yokohama-jsh.ac.jp/
十文字中 04年入試要項
1回の募集人数を120名から100名に。2回を70名から90名に。
1回 2月1日 女子100名 2科4科
2回 2月2日 女子 90名 2科4科
3回 2月3日 女子 30名 2科4科
4回 2月4日 女子 20名 2科4科
各回とも入学手続は2月8日14:00まで。2月14日までに辞退した場合は、納入金のうち施設費を返金。
各回の入試結果で特待生を発表。特待生は入学金と1年次の施設費・授業料を免除。在学中の成績により2年次以降の継続あり。
今後の行事日程
学校説明会
9月 6日(土) 10:00~
10月11日(土) 10:00~
10月28日(火) 10:00~
11月13日(木) 10:00~
11月29日(土) 10:00~
12月13日(土) 10:00~
1月11日(日) 14:00~
オープンスクール 予約制
9月13日(土) 13:00~
体験学習(クラブ活動、模擬授業等)
校内見学、個別相談等あり。
十文字祭
9月27日(土) 午後
9月28日(日) 全日
両日とも入試何でも相談開催
個別説明・相談 事前に予約(03-3918-0511)
随時(日曜・祝日をのぞく10:00~16:00)
03年大学入試結果
埼玉 信州 学芸大 都立大 国公立計
総数 1 1 1 1 4
現役 0 1 1 1 3
早大 慶大 上智 明治 青山 立教 中央 法政 理科大
総数 8 4 6 12 5 23 12 20 12
現役 8 4 5 11 4 19 10 15 8
=卒業生318名に対する東大、早慶上への現役合格者数の割合(A率)は5.3%。MARCHへの割合(B率)は18.5%。昨年のA率は7.8%、B率は19.3%。=
http://www.jumonji-u.ac.jp/high/
聖セシリア 塾対象説明会(03年7月2日)
校長挨拶 伊東校長
学校は人間形成の場。
よい教育を受けないと幸せな人生を送れない。
セシリアの生徒は明るく真面目でさわやか。
他人の悲しみを自分の悲しみとできる、美しいものを美しいと思う豊かな心と実行する力の調和を目指す。
昭和4年に創立。来年に創立75周年を迎える。
どんな時代にも変わらぬ道徳観、価値観が必要。→ セシリアはキリスト教精神に基づく教育を行う。
決して宗教を強要するわけではない。
キリスト教(カトリック)の精神を具体化して生徒を指導している。
4つの教育目標
1 基本的な知識と、その知識の獲得方法の学習から自己教育力を育成する。
2 いかに行動すべきかを体験的に育成する。
3 愛の心ゆたかに、社会において共に生きる精神を育成する。
4 人間として生きることの意味や意義を考え続けていく心を育成する。
聖セシリアの教育 服部教頭・・パワーポイントを使いながら
セシリアは生徒にとって家庭につぐ第二の港でありたい。
4つの教育目標に対応した、学習する、体験する、活動する、思索するについての具体的な説明。
1 学習する
① 授業時間数の確保のために、2002年から、二期制、70分授業、土曜講座を実施。
定期試験は前期3回、後期2回。
授業5日制だが学習機会6日制。土曜日に補習や講習を開講。
② 知育を重視する。
知育と切り離してよい判断・行動やよい考え方はできない。
知育なくして心は育たない。
③ 言語教育を重視する。
国語、数学、英語は高1から習熟度別授業。
④ ワークシートの作成。
教師手作りのプリント(オリジナル副教材)
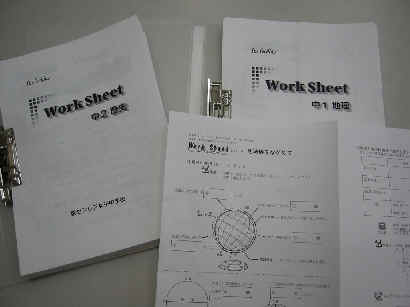
⑤ 総合学習の実施
総合学習を学習方法の修得と学際的な学習として捉える。
中学では学習方法の修得を目指した総合学習。
ex.バナナを通して世界を知る
高校では学際的な学習としての総合学習。
⑥ 中1~高1まで全て必修科目に。
幅広く学習することで生徒の進路を保証してあげる。
⑦ 高2からのコース別選択制。
2 体験する
① 学校行事。・・もう一つの学びの場。
さまざまな学校行事が組まれている。
ニュージーランド語学研修・・希望者対象で20日間のホームステイ。
② 構成的エンカウンター。
人間関係作りが苦手な生徒が増えており、人間関係作りを支援する。
入学前から中3までの間に25項目が計画されている。
③ 生徒理解から始まる生徒指導。
家庭での様子・・生活状況アンケート
家庭との連携・・保護者面談、学年懇談会、保護者向け講演会、福祉講演会
教職員研修・・各種のカウンセリング研修
自然に挨拶のできる生徒に。
3 活動する
① リビングトギャザー(課外活動)
集団の中で生徒同士が交流する場としてクラブとフォーラムを設ける。
② ボランティア(福祉活動)
テレサ会・・自由参加。
ボランティア実践講座(高1)・・必修単位になっている。
4 思索する
① 価値の教育
宗教の時間にキリスト教の価値観を通じて生き方を考える。
学校生活のさまざまな場面を通して価値観を形成してゆく。
② 教養選択
自分たちの生きている世界を深く知り、どう関わるかを考える。
高3に設置。7講座の中から1つを選ぶ。10数年前から実施。
③ サマーセミナー
高3で生きるをテーマに3泊4日で実施。
講話、映画鑑賞、ディスカッション、発表など。
その時のノートが生徒達の人生の支えになっている。
④ キャリアガイダンス
高校3年間、各学年で週1時間ずつ継続して行う。
入試要項に関して 西澤副校長
03年入試結果
1次 2次
募集人数 90 30
応募者数 148 206
受験者数 139 93
合格者数 99 52
合格最低点 94 101
(200) (200)
120名が入学。4クラス編成。
04年入試要項
3回入試に。2回、3回は2科4科選択に。
1次 2月1日 女子80名 2科 面接
2次 2月3日 女子25名 2科4科 面接
3次 2月4日 女子15名 2科4科 面接
判定は、1次は国算の合計点で。足切りはなし。
2次、3次はまず国算の合計点で、次にそこでの合格者を除いた残りの4科目受験生を4科の合計点で。
2科と4科の合格者の比率は出願状況によって判断する。
重複受験の場合、従来のデーターでは再挑戦した受験生の25%が合格している。
繰り上げ合格を出す場合は複数回受験生を優先する。
繰り上げがある場合は2月10日くらいまでに電話で連絡。
帰国生は判定に際して海外での経験を配慮する。
帰国生は試験当日に面接あり。
学校は生徒達に体系的に教えることが必要。トピックス的な学習やカフェテリア風の選択では力にならない。
総合学習を行うにも基礎が必要。
中高で、生徒達が本当にやりたいことを選択できる力をつけて上げることが必要。
各教科より
1 国語
① 出題趣旨
・総合的な記述力と読解力を図ります。
・「考えたことを文章でまとめる」といった力は、人と人とのつながりの中で生きていく上では必要不可欠な力ですのでウエイトをおくように考えています。
・受験の機会にその文章を読むことで、何らかの発見や得るもの残るような内容の文章を出題したいと考えています。
② 出題傾向
・問題の構成は大きな設問が3つ、1番が漢字、2番、3番が文章読解の問題です。
・漢字は小学校で学習する教育漢字の範囲で書き、読み共に出題します。送りがなも含めて問うものもあります。例年読み書き合わせて10問程度になります。
・文章読解は、一つが小説や随筆のような文学的文章、もう一つが説明文・論説文と言われる説明的文章になります。
・読解する文章の分量はどちらも大体2500字から3000字程度のものとなるようにしています。
・問題の形式は、記号を選択して答えるような客観式の問題と文章を使って自分で文章をまとめて答える記述式の問題がありますが、配点としては全体の40%ほどが記述式の問題になります。ただし、記述の問題は完全解答というのは難しいので、その必要とされるキーワードが入っているかどうかや、理解の度合いによって中間点をつけるようにしています。
③ 出題に関して
・内容についても特定分野の専門的な知識がないと読みとれないようなものは出題しません。小学校6年生にとって言葉の意味が難しいと思われるものには注釈をつけるようにしています。
・小学校6年生の教科書の文章よりは、少し難しいものを読みとれる力が必要ですので、日頃から多く、手応えのある文章に触れる機会を作っていただければと思います。
2 算数
① 出題趣旨
・中学数学を学習するにあたって、必要となる基礎知識、技術があるかどうかを図ります。確実な計算力や単位の換算、割合の利用、比例やグラフの読みとり、図形に関する基礎知識、技術があるかどうか、ということです。
・特殊算などの入試問題の基本となるものを、きちんと身につけているかどうかを図ります。入試に向け目的意識を持った学習姿勢があったかどうかを図ることにもなります。
・問題解決的な思考力があるかどうかを図ります。つまり新しい事態に遭遇したとき、それに対処する能力があるかどうか、ということです。
② 出題傾向
・極端に難しい出題は避け、全体として基本的な問題を出題します。
・来年の問題は、今年よりは易化させ、問題数を減らす予定です。
・形式は例年と同様です。例年は、大問が7~8題で、1番が計算問題と単位や割合の換算で8問程度、2番、3番が3~4行程度の特殊算を中心とした文章問題、これが6問程度、4番以降は年によって出題順は違いますが、ほぼ毎年出題しているのが図形の求角・求積の問題、比例の定義に関連した問題、グラフの読みとり、規則性です。
③ 出題に関して
・難易度は3回の入試ともに同程度にします。
・出題範囲は、新指導要領で削除されたり、軽減されたりした内容の扱いに関しては、組み合わせたり、発展的に考えることで解決できる問題は従来通り出題します。例えば台形の面積、帯分数や分数・小数の混合計算、小数点第2以下の計算、統計などです。円周率は3.14を使うように指示します。また、比例の関係などもxやyなどの文字を使います。また、完全に削除された内容、例えば図形の対称移動、拡大縮小、円錐、反比例などについても、出題する場合があります。ただし、その際は注釈をつけるなど、設問のしかたを工夫します。
・途中過程も配点に加える意味で、式をたてたり、考え方を問う出題もします。そのような問題では、答えが間違えていても、式や考え方で中間点が加わることになります。
3 理科
・生物と環境、物質とエネルギーの2領域から出題します。中学で学習する事項の基礎を問います。
4 社会
・総合問題2割、歴史8割の配分で出題します。
・歴史は聖徳太子から明治の終わりまでで、歴史に関する地理を含みます。
・総合問題は戦後についての総合問題を出します。
(報告 A.A)
クラブ活動体験見学会
7月26日(土) 10:00~14:00
各クラブの体験ができます。見学も可能。
時間内であればいつでも可。予約は不要。
入試相談コーナーあり。
http://www.cecilia.ac.jp/
日大豊山女子 04年入試要項
1回 2月1日 女子85名 2科4科
2回 2月3日 女子20名 2科4科
3回 2月5日 女子15名 2科4科
http://www.buzan-joshi.itabashi.tokyo.jp/
普連土学園 教育内容(7月3日 全私学新聞)
普連土学園中学校・高等学校(畠中ルイザ校、東京都港区)は、一八八七年、キリスト教フレンド派(クエーカー)の人たちによって女子教育のために作られた学校である。簡素の精神を旨とし、当初から手作りの教育を実践してきた。現在も「小さいことはよいことだ(small is beautiful)をモットーに、一学年三クラス(一クラス四十五人)と小規模。中高完全一貫の中で行き届いた教育を行っている。
なかでも、創立当初から行ってきた宗教教育・ボランティア活動・体験学習を、建学の精精神(神の種子を育てる)を実践するものと位置づけ、HRの時間や聖書(宗教)の授業、学校行事を通してさらに活発化させている。例えぱ、普連土学園の一日は始業前の礼拝で始まり、終拝で終わる。月曜・火曜は講堂で全校礼拝。水曜は各自が心の中で神との対話を心がける二十分間の「沈黙」。木曜はクラスでのホームルーム礼拝。金曜は中高の自治会役員の担当による全校礼拝を行う。礼拝の中では、教職員や生徒たちが順番にみんなの前で“お話”をすることになっており、内容の多くは日常の経験を踏まえたものだ。最近の生徒の発表では、「イラク戦争をただ見ているだけではなく、平和維持に自分がいかにかかわっていくか」「報道は報道する側にとって郡合のよい報道がなされるため、自分できちんと見極めなけれぱならない」「幼児期に大切にしていたおもちゃを、周りのプレッシャーもあって捨ててしまったけれども、これからは自分にとって大事なものを大切にしたい」「自分を肯定できるようになった」など、生徒たちの心の働きや思いが感じられる話が多い。聞く側の生徒たちがそれを自分たちのこととして共感するというだけでなく、何より“お話”をした生徒がその後精神的な成長を見せるという。
ボランティア活動・体験学習については、中学一年生から高校三年生まで、成長に応じたプログラムが組まれ、
学年ごとにテーマに沿って実施されている。中学一年のテーマは「視覚障害について。」まず盲導犬を連れた視覚障害者の方からお話を聞き、その後、アイマスクをし白づえを持って校内を歩くという体験をする。点字も学習する。中学二年のテーマは「聴覚障害について」。聴覚障害者の講演を聞いたり、手話を習う。生徒はたいへん覚えが早く手話で聴覚障害者と話せるようになる。最近、聴覚障害をもつピアニストに講演をしてもらったところ、生徒たちは大変感動し多くの示唆を受けた様子だった。中学三年では「身体障害について」学習する。生徒たち自身が車いす体験をすることによって、街路に潜む危険性に気づくようになる。高校一年は「知的障害について」がテーマとなる。知的障害は接する機会も乏しくどのようなものなのかという理解が難しい。そのため、まず卒業生で知的障害児を持つ方に来ていただいて話をしてもらい、理解を深める。その後全員が、小人数に分かれてる。こうした活動の後では、生徒は知的障害も他の身体の障害と同じく一つの特徴であり、共に社会をつくっていくことが大切だと認識するようになる。高校二年生には「高齢化問題について」をテーマとして与えている。講演やビデオなどで、高齢者は障害を複合して抱えている存在であることを認織させた上で、高齢者の生活を疑似体験させている。高校三年では「奉仕活動のまとめ」として、これからの生き方を話し合う。ボランティア活動の時間は学年で差があるが、だいだい年間十時間。そのほかに一日体験も盛り込んでいる。この幅広いボランティア活動を裏で支えているのは、教職員、卒業生や保護者である。高校一年生の一日体験では福祉に携わる卒業生が体験先を紹介してくれた。最近では施設側も非常に協力的で、生徒を快く受け入れてくれる。とはいえ、あいさつの仕方から言葉づかいまで、生徒たちへの細かい指導は欠かせない。施設体験では、熱心に車いすを磨いたりして普段とは別の顔を見せる生徒もいる。
自分の目常に感謝の気持ちを持つようになり、体験後自主ボランティアを始める生徒もいる。このような活動を通して、人を思いやる気持ちが芽生えるだけでなく、人から必要とされることの喜びも知ることができる、とボランティア担当は言う。
しかし、奉仕活動に時間を割くことで進路に支障を来すのではないかという懸念に対して、畠中校長は「進路と奉仕は対立しているものではなく、生徒たちが自分のことを学び、知る、大切な機会ですので、応援してくださいとお願いしています」。そして「学園は生徒にも、卒業生にも、安心できるところ、もう一つの家庭です」と言う。使い込まれた木作りの机やいすにも家庭の温かさが感じられる。生徒たちが迷路のようだと言って喜ぶ独特のデザインの校舎も築三十五年になる。最近、耐震補強を施した。畠中校長は「素晴らしい校舎です。あと五十年は使いたいです」と話されている。
http://www.friends.ac.jp/
横浜雙葉 04年入試要項
入試日が2月1日から2月2日に。
2月2日 女子90名(帰国生若干名) 4科 面接
面接は受験生と保護者1名。
面接日は1月11日、12日、17日、18日、24日、25日を予定。
横浜雙葉の総合学習について(説明会より)
中1総合学習
自分とのかかわり、人とのかかわり(中1主任 木下庸子)
昨年、一年間、中1の担任として総合学習を実施させていただきましたので、お話しさせていただきます。
1 中1の総合の概要
中1総合学習がどのようなものか、ですが、中1は、中2から本格的に始まる総合学習の「基礎」として、「総合学習に必要な基本的スキル(技法・技術)を身に付けること」が、その主要な目的です。
スキルといってもいろいろありますが、ひとつには、学習スキルといいますか、総合学習に必要な正に技術です。 図書館での資料の調べ方、インターネットでの調べ方、グループ討議のしかた、発表のしかた、ディベートのしかたなどです。
一方社会的スキルとして、人に何かを頼む方法、断る方法、人の前で話をする方法、聞く方法などを取り上げます。
2 見えてきたこと、気づいたこと、気づかされたこと
総合学習を一年間行いまして、総合の授業がスタートした初年度ということで、いろいろな発見、予想しないこと、あるいは期待以上だったものなどがありました。その中で、いくつか私の心に残ることについて、お話したいと思います。
(1)ディベート
学習スキルの中のひとつ、ディベートを行ったときです、ディベートにについて、3週間くらいかけてかなりみっちりとそのやり方を学んだあとで、実際にディベートを行いました。テーマは「英語は小学生から学ぶべきか、否か」とか「野菜はすべて無農薬にすべきか、否か」といったものです。
ひとつの班が6人ずつでチームを組んでディベートをしました。勝敗を一応決めるとあって、みんなやる気満々で、集めた資料をもって、のぞんでいました。あるチームには、いつもは目立たない生徒がメンバーとなっていました。彼女は口下手で、読書が好き、人とも積極的に話せない。だから私は、内心、その生徒がどうディベートで話していくのか、心配でした。せっかくみんながやる気をだしているときに、熱気を冷ますのでは、とか思っていましたし、彼女がうまくできなくて余計、クラスの中で浮いてしまうのでは・・・と。ところが、実際にディベートが始まると、彼女はすごい論理立てで話すんです。(本をよく読んでいるから?)相手チームの鋭い質問にも、とうとう反論していったのです。クラスからは思わず拍手が起きたほどです。
少し打ち解けていなかったかなというその生徒もこのときから、クラスのみんなと本当の意味で打ち解けました。
(2)沈黙する
社会的スキルとして、「沈黙する」といった練習を行ったときでした。最近の若い人の傾向として、だれかと話していると安心する、というか話をしてないと安心しない、という傾向があると思います。いろいろ原因があるだろう。でも、時には「自分自身の内面を深く見る」「自分の内面と対話する」ということが必要であろう。そこから新しい発見がある。そういうことで、こういう訓練がプログラムに入っています。といっても45分間ずっと沈黙ではなく、導入をして5分から10分、目を閉じて身体の力をスーッと抜いてじっと座っています。
最初は、おしゃべりする人、目をいつまでも開けている人、ガタガタ身動きする人などいました。でもしばらくするとシーンとなってきました。あとで生徒に聞いてみると「黙っていることも結構いいものだ」「久しぶりだった」とか。若い人は、今1人でいることは自分の部屋であるけれど、音楽がなっていたり、携帯がなっていたり・・・という感じらしいのです。
「自分の小さいときのことを思い出していた」「無になろうとした」なかには「眠ってしまいそうだったが、すごく気持ちよかった」とか、何人もが「うちでもやってみた」「これから時々やってみたい」とか感想を述べていました。
意外な面を発見した感じです。生徒自身も、自分の意外な面を発見したのでは。
(3)合唱コンサート
もうひとつ、昨年の私のクラスでのエピソードで、総合学習の時間以外で、総合学習で学んだことが生きてきた、実際の生活の中で生かされた、と感じたことをお話したいと思います。
それは、本校で毎年一月にクラス単位で行う合唱コンサートに際して、クラスで歌う自由曲の曲目を決めるときでした。合唱係が数人いるのですが、彼女らが選んだ曲が実はクラスのメンバーには気にいらなかったのです。生徒の1人が手をあげて「別の歌がいいと思います。」と言ったところから始まりました。合唱係に言わせれば、「みんなに意見を求めたのに、何も意見が出ないから合唱係が決めたのに何をいまさら」だったようです。
意見があちこちから出て、なんだか険悪なムードになって、私はつい口をだして「あの・・・まあお互いの意見の違いはともかく・・・」と仲介に入ろうとしたら、生徒に「先生はちょっと黙っててください」と言われました。「あ、はい」といって引き下がりました。それ以後は見守っていたのですが、結局うまくいったのです。どちらも、わがままを通すのではなく、きちんと言うべき主張を言い合い、何が原因で今のようになっているかを考え、結局「明日までに別の曲をみんなで探す。探してなかったら合唱係の決めた曲にする」「最終的に決まった曲には文句を言わない」など約束事も決めたようです。そして結局、新しい曲が選ばれ、みんな文句をいわず、それ以後はその曲の練習に全力をだし、本番では全員の心がひとつになって、本当にすばらしい曲を歌うことができました。
私は、このときの生徒の様子、物事を決めていく手段を見ていて、総合学習で学んだディベートや、会議の仕方、あるいは個々の生徒の「論理的考え方」などが、自然とうまく生かされているんだなぁ、と感じました。そうでないと、多分うまくクラスとしてまとまらなかったと思います。その後の練習でみんながやる気を持っていたのは、こうしたプロセスがあったからだな、と思います。
その他
一年間の授業の中で、教師と生徒とが一緒の方向を見ていると感じた瞬間がありました。普段は教師が教える側、生徒が教えられる側という形ですが、総合学習では生徒と一緒に歩んでいるという感じがありました。
http://www.yokohamafutaba.ed.jp/
青山学院 03年大学入試結果
東大 京大 農工大 芸大 お茶の水 横国大 学芸大 国公立計
総数 2 1 2 1 1 3 1 11
現役 1 0 1 1 0 3 1 7
早大 慶大 上智 明治 青山 立教 中央 法政 理科大
総数 17 19 11 4 365 7 6 3 5
現役 12 14 8 2 364 5 4 3 2
=卒業生457名に対する東大、早慶上への現役合格者数の割合(A率)は7.7%。MARCHへの割合(B率)は82.7%。青山学院現役合格者のうち357名は推薦での合格。昨年のA率は7.3%、B率は80.2%。=
http://www.jh.aoyama.ed.jp/
秀光中等教育学校(仙台育英) 04年東京会場入試
α 1月11日 男女20名 4科 慶応大学三田キャンパス
β 1月18日 男女20名 2科4科 青山学院大学青山キャンパス
γ 2月 7日 男女若干名 仙台育英学園千代田校舎
各回とも奨学生選抜を含む。奨学生は初年度の授業料免除。次年度以降、奨学生試験の結果により授業料 の免除あり。
学校説明会 申込はFAXで
8月26日(火) 11:00~15:00 学校にて
授業見学、寮見学、寮の食事試食会あり
9月28日(日) 10:00~11:30 東京会場(慶応大学三田キャンパス)
在校生との懇談会あり
FAX:022-368-2800
詳細は電話で(022-368-4111)
http://www.sendaiikuei.ed.jp/s_html/s_top.html
入試情報
合同招集日 04年は2月8日に
麻布、開成、駒東、筑波大駒場、栄光、聖光の合格者招集日が04年は2月8日(日)13:00に。
渋谷幕張の招集日も同じ2月8日に。
主な入試日程 神奈川地区男子
2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日
栄光学園 ○
聖光学院 ○ ○
浅野中 ○
サレジオ ○ ○
鎌倉学園 ○ ○ ○
逗子開成 ○ ○ ○
桐蔭学園 ○ ○ ○
桐光学園 ○ ○ ○ ○
法政二中 ○ ○
横浜中 ○● ● ○
(●は午後入試)
公開模試情報
首都圏模試7月 統一合判(7月6日)
昨年の7月はどの模試とも競合せず。今年は日能研と競合していながら昨年比8.0%の増加。男子は7.6%の増加、女子は8.5%の増加。
03年 02年 01年 00年
男子 4科 4623 4252 4030 3691
2科 783 774 832 833
女子 4科 4084 3552 3041 2687
2科 1925 1988 2200 2591
合計 11415 10566 10103 9802
日能研模試7月 志望校選定(7月6日)
昨年は四谷大塚と実施日が競合。今年は首都圏模試と実施日が重なる。昨年比4.7%の増加。
男子は6.4%増。女子は2.8%増。
03年 02年 01年 00年
男子 4科 7767 7126 7050 6483
2科 562 700 477 617
女子 4科 6083 5492 5120 4791
2科 1377 1765 1948 2185
合計
15789 15083 14595 14076
教育情報
教員異動 現行の8年から3年に、東京都が来年度から大幅短縮
(毎日新聞 7月10日)
東京都教育委員会は10日、公立小中高校教員の定期異動の間隔を来年度から現行の8年から3年に短縮することを決めた。同じ学校での勤務が長い「古参教員」を排し、校長が学校運営にリーダーシップを発揮できるようバックアップするのが狙い。しかし、校長による恣意(しい)的な人事につながり、落ち着いた現場教育ができないといった批判も教員から出ている。
都内の公立小、中、高校の一般教員は約5万2000人。都の定期異動実施要綱では、異動の対象となる教員は、初任地で4年以上、2校目以降は8年以上勤務となっている。要綱を改正し、異動対象を赴任校数にかかわらず1校あたり原則3年勤務した教員とする。校長の裁量があっても最長6年と期限も設ける。定期異動サイクルの短縮化は、教育現場の活性化にもつながると都教委は期待している。
また、都教委は05年度から順次導入する計画の都立中高一貫校の入試方法について、都立高校と同様にスポーツや文化活動など何らかの分野に秀でた生徒を優先的に入学させる「一芸枠」を設けることも明らかにした。一貫校は、都が10年度までに10校を設置する予定。
数学オリンピック 世界の頭脳”と対決、東京で開幕
(朝日新聞 7月12日)
世界の若者が数学で競う第44回国際数学オリンピックが12日午後、東京・代々木のオリンピック記念青少年総合センターを主会場に開幕した。初めての日本での開催だ。過去最大規模の83の国・地域から約700人の選手団がやってきた。地の利を得た6人の日本選手が迎え撃つ。
スロバキアから来たハナ・ブダチョワさん(18)は12日朝、「初参加でわくわくする。数学はもちろん好きで、数学者になるかどうかわからないけど、関係のある学問をしたい」と話した。
日本代表として中学2年から連続5回出場の大島芳樹君(17)は「99年のルーマニア大会は食事が口に合わなくて苦労した。国内なら心配ない」と自信を見せる。入江慶君(16)は「海外に行けないのはちょっと残念だけど時差もないし、目標は金メダル」。
主催する数学オリンピック財団の話では、日本代表の6人は約1200人が参加した日本数学オリンピックの成績優秀者から、2回の合宿で選ばれた。
元代表で今回団長を務める河村彰星(あきとし)さん(21)=東京大4年=は2年前、財団の財政難で開かれなくなった夏合宿を手弁当で復活し、若手の面倒を見てきた。「合宿で同じぐらいの年の数学好きと話をすると楽しい。夏合宿は格別だったから」と話す。大会を、そんなきずなを共有する元選手らが文字通り支える。
◇
日本代表の6人の高校生は次のみなさん(敬称略)
入江慶(筑波大付属駒場2年、東京、初出場)▽大島芳樹(同3年、東京、5回目)▽尾高悠志(同3年、神奈川、3回目)▽足立潤(栄光学園3年、神奈川、初)▽長坂友裕(愛知県立岡崎3年、愛知、初)▽西本将樹(灘2年、兵庫、2回目)
◇
<国際数学オリンピック> 数学的な才能に恵まれた高校生以下の若者を見つけ、育てる目的で59年からほぼ毎年開かれ、今年が44回目。日本の参加は90年の北京大会から。代表6人の得点合計で競う。国別順位で日本は92年(モスクワ)の8位が最高。昨年(英グラスゴー)は84カ国中16位。中国が4連覇中で、米ロや東欧諸国が強い。
その他
保護者アンケート結果 (協力 アクセスの6年生保護者)
男子校か共学校か
1 受験校を決める際に
男子校を選ぶ 22 57.9%
共学校を選ぶ 1 2.6%
こだわらない・未定 15 39.5%
2 男子校を選ぶ理由
女子のいない(女子を意識しない)環境で過ごさせたい
本人が男子校を希望(女子と一緒は嫌という)
進学実績の良い(優秀生が集まる)学校が男子校だから
共学校は男子と女子の偏差値の較差が大きく、女子が主導権を握っている。
共学校なら公立でも良い
共学校には大学附属が多くその中に中学から入れることに抵抗がある
魅力的な共学校がない
男らしく育ててもらえそう
男社会での経験も楽しいと父親が言うので
男子のさまざまなタイプの友達ができる
男どうしの中で一生つき合える友達を見つけて欲しい
希望した学校が男子校だった
男子校の方が子供に合っていると思える
落ち着いて学校生活(勉強・クラブ活動等)に取り組める
3 共学校を選ぶ理由
共学校の方が本人に合っていると思う
共学の方が自然
4 こだわらない・未定の理由
教育環境が良ければどちらでもよい
校風が子供に合っていればどちらでもよい
教育内容が重要
男子校・共学校それぞれに利点・欠点がある
本人が望むところであればどちらでもよい
女子校か共学校か
1 受験校を決める際
女子校を選ぶ 20 51.3%
共学校を選ぶ 2 5.1%
こだわらない・未定 17 43.6%
2 女子校を選ぶ理由
伝統校は女子校が多い
進学実績の良い学校は女子校に多い
女性の能力を引き出すという点で女子校の方が実績と経験がある
女子だけの方がリーダーシップをとる機会が増えそう
男子に頼ることなく女性として、人間としてしっかり考え行動する態度を養える
女性としての自立心を学べる
学習面で男女の違いに合わせた理解のさせ方ができる
規律の厳しい女子校に行かせたい
男女別の方が落ち着いた学校生活が送れる
異性を意識することなく自分らしさを発揮できる
同性の友人が多くでき、将来の女同士の人間関係が円滑にいくよう訓練できる
心が許せる友人や先生と多く出会える
自分も女子校で学んだ
女子校の方が数が多い
魅力のある共学校がない
共学校は男女で成績(偏差値)の差が大きい
共学校には附属校が多く、そのまま上まで行ってしまう
共学校は男子、女子の性別にこだわってしまう気がする
共学校は学費の高い学校が多い
本人が女子校を希望
本人の希望した学校が女子校だった
3 共学校を選ぶ理由
共学の方が自然
女子だけだとぎすぎすした雰囲気になってしまいそう
本人の希望
4 こだわらない・未定の理由
校風が子供に合えばどちらでもよい
教育方針・教育内容・教育環境で選ぶ
先生方の生徒に対する意識や熱意、学校の雰囲気を考慮して決める
女子校・共学校それぞれに利点がある
共感できるものがあればよい
子供の性格がどちらに合っているかわからない
本人の希望を優先
平均寿命 女性の平均寿命、85歳超える
(朝日新聞 7月12日)
日本人の平均寿命は女性が85.23歳、男性が78.32歳となり、ともに過去最高を更新した。11日に厚生労働省がまとめた02年の簡易生命表でわかった。女性は初めて85歳を超え、世界一の水準で長寿化が進行している。02年に生まれた赤ちゃんのうち、男性は54%強、女性は76%が80歳まで生きられる見通しだ。
平均寿命は前年に比べ、女性は0.30歳、男性は0.25歳延びた。男性は自殺者の増加がマイナスに響いたものの、がんや脳血管疾患で死亡する人の割合が減り、全体的に高齢者の死亡状況が改善されたことが大きい。この10年でみると、男性が約2.2歳、女性は約3歳、平均寿命が延びた。
主要国・地域との長寿比較では、統計の年次やとり方が異なるものの、男性は(1)香港(02年暫定値、78.7歳)(2)日本(3)アイスランド(00~01年、78.1歳)、女性は(1)日本(2)香港(84.7歳)(3)スイス(99~00年、82.6歳)の順だった。
簡易生命表は、その年の年齢別の死亡状況が今後も変化しないと仮定した場合、各年齢の男女があと何年生きられるかを示す平均余命などを算出したもの。0歳児の平均余命が平均寿命と
塾主催私学経営セミナー 136校が参加
大手塾主催の私学経営セミナーが品川プリンスホテルで開かれ、136校から261名の先生方が参加。参加費用は1名12500円。生徒の学費から参加費用を支出(自前で参加費用を払った方もおられるかもしれないが)して3名以上参加した学校は以下のとおり。
郁文館、小野学園、神田女学園、共立第二、麹町学園、佼成学園女子、駒沢学園、品川女子学院、渋谷教育渋谷、十文字、城西大城西、聖徳大附属、青稜中、多摩大聖ヶ丘、多摩大目黒、富士見丘(渋谷)、普連土学園、武蔵野女子学院、明星中、目黒学院、目白学園、八雲学園、山手学院
<問題>
下図は、正三角形の各辺をそれぞれ三等分、四等分した図です。
(1) 各辺を三等分した図では、色のついた部分の面積は、正三角形の面積の【 】倍です。
(2) 各辺を四等分した図では、色のついた部分の面積は、正三角形の面積の【 】倍です。
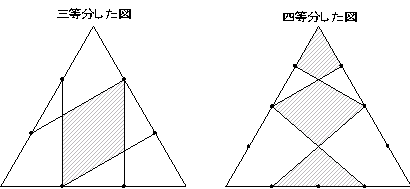
(03年芝1回)
入試問題に挑戦第83回解答編
<問題>
ある仕事を、毎日14人が働く予定で始めました。最初の70日間は予定通りに進みましたが、71日目からは12人しか働けず、仕事は予定より10日遅れました。次の問に答えなさい。
(1) この仕事は何日間で終わる予定でしたか。
(2) もし12人を途中から15人に増やして最後までこの仕事をしていれば、仕事の遅れは4日間ですんだはずです。15人で何日間仕事をすればよかったですか。
(03年海城1次)
<解答>
仕事算では、人数と日数が反比例(逆比)になることを利用します。
(1)14人の予定が12人に減ったということは、人数の比は7:6なので、かかる日数の比は⑥:⑦になります。
ここで、日数の差の①にあたるのが10日になるので、予定日数は、
70+10×6=130(日間)
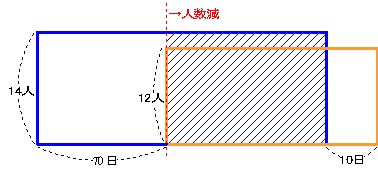
(2)同様に、12人を15人にすると、人数の比は4:5なので、かかる日数の比は⑤:④になります。
「遅れが4日」ということは、「10日遅れ」から「6日短縮」したことになるので、日数の差の①が6日。
よって、15人で仕事をする日数は、
6×4=24(日間)